それでも共同性を展望できるとしたら
貴戸:ひとくくりにLGBTQと言われることが多いですが、当事者といっても、ほんとうにさまざまで、トランスジェンダーにおいては、とくに特例法との関係で問題が顕在化したところがあったわけですね。私たちは、不登校・ひきこもりを地場にしていますが、やはりひとくくりにはできない。その人の環境や関係によっても異なるし、その後をどう生きているかで、経験の意味づけは変わってくる。それでもなお、不登校・ひきこもりを軸に何らかの共同性を展望するとしたら、どこに軸足をおいたらいいのか。そのあたりが一番考えたいところです。「正当な当事者」ではない、当事者運動からも漏れ落ちたところから、つながっていくこともあっていい。そこで生まれた知恵は、ほかの漏れ落ちた当事者にも使えるかもしれないと思うんですね。トランスジェンダーにおいても、さまざまなちがいのなかで、それでも何らかの共同性を展望するとしたら、どのあたりが課題になるとお考えでしょうか。
吉野:たしかに、特例法によって分断や対立が見えやすくなったところはありますが、それ以前から、それぞれの当事者の価値観や基準によって、分かれてしまっている部分はあったと思います。たとえば、望む性として生活できている人と、できていない人で大きなちがいがある。その人たちが、ひとつになるというのは難しい。いまの若い世代、性への違和感やもやもやは医学的に対処できるものだという情報のもとで育ってきた人たちは、第二次性徴を止めるブロッカーを使ったり、早い段階からホルモンを打ったりできる人もいます。出生時と逆の性になるには、若いうちからのほうが適応しやすいんですよね。そういう人たちは「性同一性障害」の当事者という意識が希薄でしょう。望む性として生活できているという実績、実感が大きいわけですから。もちろん親の無理解など、さまざまな条件で医療にアクセスできない人もいて、そういう層はある程度の年齢になってから、望む身体を得るためにお金を稼いで、学業や仕事を中断したり、自分の過去を知られていない環境で新たな生活を始めたりする。移行後の人生のスタート地点が大きく異なると、階層もはっきり分かれてしまうと思います。
貴戸:ご著書のなかで印象的だったのは、ずっと「移行中」であるところから、社会を見返していくとおっしゃっていたことです。特例法は、社会の仕組みはそのままに、一部の人の性別移行を特例的に認めるというものですよね。でも、男か女かの二分法ではなくて、そのあいだがいっぱいある。二元論の社会そのものを見返していかないといけない。つまりは、マジョリティに変更を迫っていくことが重要だと。でも、一方では、自分の人生における幸福を追求することも大事で、社会を変えていくモチベーションを維持し続けるのはたいへんだとも思います。
吉野:トランスジェンダーの状態を生き続けるというのは、そうしたくない当事者のほうが多いと思います。だって、たいへんですからね。この社会は男性か女性かで設計されてしまっているので、どちらかに沿って生きていくほうが楽ですし、そう生きていかざるを得ないところもある。ほんとうは、性自認がハッキリと女性か男性かではない人でも、生活していくために、女性か男性かのかたちをとっている人も多いように感じています。
ただ、最近は個人が発信する手段ができてきたので、以前よりは、いろんな当事者が発信し始めています。私も、「ノンバイナリーのタイプのトランスジェンダー」と名乗って発信しています。でも、社会が男・女のバイナリーで設計されている以上、そうではない表現を当事者がしていても、男・女のどちらかで理解されてしまうんですね。本人としては移行中、トランスジェンダーであると示しているつもりでも、それを受けとるチャンネルがない。
山下:話が核心に入ってきたように思います。いろいろ質問したい人もいるかと思いますので、ここからは、オンラインでの参加者にもふってみたいと思います。いかがでしょう。
バイナリーな社会のなかで
山崎:神奈川で「語る会」という会の世話人をしたり、新ひきこもりについて考える会に参加している山崎と言います。トランスジェンダーの当事者といっても、男か女かどちらかでパスしてしまえば、わざわざ言うことはないという人もいます。周司あきらさんも、聞かれたら最小限のことを伝えて、なるべく波風立たないようにすると書いていました(周司あきら著『トランス男性による トランスジェンダー男性学』大月書店2021)。そうでないと生活がうまくゆかないからと。じゃあ、そこで当事者の連帯はどう考えられるのかというと、たしかに難しいですよね。
中島潤さんも、自身がそうであるノンバイナリーあるいはXジェンダーの当事者は、マイクロアグレッション(*3)にさらされていると話していました(中島潤「Xジェンダー/ノンバイナリーの人々が受けるマイクロアグレッション」2021年12月5日講演)。身体に違和感がないならたいしたことはないと言われたり、男か女かどっちなのかと問われる。しかし、そもそも、数ある特性や属性のなかで、なぜ性別がこんなにも問われるのか、男女二分法で分けられたうちのどちらかでないといけないのか、と。ただ、可能性を感じるのは、そういう問いかけが発信されはじめていて、制度も変わってきているところですね。アメリカでは、パスポートへの性別記入欄で、男(M)、女(F)以外にX(ジェンダー)という表記の選択が認められましたね。そういうところは希望ではないかと思います。しかし、バイナリーな体制は強固に残っている。そういう状況について、どう考えておられますか。
吉野:Xジェンダーというのは関西のコミュニティから出てきた言葉で、私はあまり自分にはなじまなかったので使っていませんが、私も、「正規医療を利用する正当性に欠ける」とか言われてきましたし、一昔前までは、身体を大きく変えている人ほど本気度が高いとか、本物の当事者であるかのような感覚があったと思います。
いま、ノンバイナリーを名乗る人は出てきてますし、性別欄でも男性・女性以外の選択肢が出てきているので、ちょっとずつ変わってはきている。けれども、基本的な社会の仕組みが、男性か女性かのバイナリーにできているので、ノンバイナリーで生きている人の表象や態度、発信しているものが、どう受けとめられているのかですよね。
たとえば、出生時は女性だけど男性として扱ってくださいというのは、まだ理解されやすいけど、ノンバイナリーですと言っても、どう扱っていいかわからないし、ロールモデルもない。男女どちらでもない扱いというのを社会が経験していないから、どうしていくかは個別に調整していくほかない。そして、そのコストは当事者が引き受けざるを得ないという困難があると思います。
医療にしても、ノンバイナリーで身体をいっさいいじらないで医療とかかわりなく生きている人もいれば、私のように一部の手術は必要だという人もいる。同じノンバイナリーでも必要とする状況はちがう。ノンバイナリーだからコストが少ないというわけではない。でも、世の中ではそうは認識されてない。
昨年12月にマンガ家のペス山ポピーさんとオンラインイベントをしたんですが、その企画は、出生時女性のノンバイナリー、Xジェンダー、ジェンダークィアに向けての企画でした。そこで一番多かった質問は、「自分はノンバイナリー、Xジェンダーとして生きていこうと思っているけれども、実は自分のなかにミソジニー(女性嫌悪)があって、女性役割を拒否したいからノンバイナリーと言っているだけなのかもしれない」とか、「女性役割を引き受けたくなくてXと思い込んでるだけかもしれない」というものでした。それだけ、社会のなかに女性差別があったり、ジェンダー規範の圧が女性にかかっているということだと思います。
山崎:女性差別やジェンダー規範が関わっているというのは私も感じます。たとえば、女性学会を中心にジェンダーフリーを推進していましたが、それに対して、ジェンダーフリーバッシングが起きました。そのなかに「中性人間をつくろうとしている」というものがありましたね。それに対して女性学会は、「性別をすべてなくす(性別消去、ジェンダーレス)とか、みんなを中性にしていくことを求めているのではなく、性別による「不必要・不適切な区別」をせず、ジェンダーの抑圧から解放されることをめざす」というかたちでバッシングする側に譲歩してしまった(日本女性学会ジェンダー研究会編『Q&A男女共同参画/ジエンダーフリーバッシング――バックラッシュへの徹底反論』明石書店2006)。こういうかたちで不十分に対応・反論してしまったから、かえって性別二分論を強化してしまったところがあるのでは?(女性学会の内側や周辺でもこの対応に批判的な意見(*4)がありましたが)。この対応が後々までたたっていて、ジェンダーフリーという言葉はタブーのようになって議論されなくなってしまいましたね。
吉野:私が大学生のときにも、ジェンダーフリーバッシングの影響は受けました。当時のジェンダーフリーに関する政府与党のワーキンググループの議事録を読むと、そこで言われているのは家族制度の維持強化ですよね。戸籍性別変更のための特例法で、子どもを持っていないことという条件(いまは未成年の子を持っていないという条件になっている)がついたのもそうですが、母は女、父は男という前提を崩すことができない。そういう家族観や家父長制に対抗する言説を強く出すことができずに、向こうの言い分にのるかたちで物を言ってしまったところがありましたよね。「ジェンダー役割を解体したからといって、中性人間になるわけではありません」とか、「ひな祭りや子どもの日がなくなるわけではありません」とか。それ以降、ジェンダーフリーという言葉が忌避されるようになったのはほんとうに惜しいことだと思います。
トランスジェンダーが、なぜ自分をトランスだと思うのかと訊かれるとき、とくに出生時女性のトランスに向けられるのは、「女性って、思春期には男の子っぽくなる時期がある」とか、「大人の女性になるのがイヤでそれを拒みたくなる時期がある、あなたもそれじゃないの」とか、本人の言い分を疑っていく、懐柔しようとしていく言い方があります。そういう言い方は出生時男性のトランスには向けられない。
あるいは、出生時女性の人が男性として生活しようとしたとき、FTMのコミュニティに行くと、そのなかでのホモソーシャリティがきついという経験を語る人もいます。周司あきらさんも、ジェンダーを男性に移行して、そのことを強調しようとするあまり、有害な男性性をなぞってしまったり、過剰に男性性を獲得してしまったりすることについて書いています。そこにしんどさを感じて、うまくやっていけなくなる人もいる。しかし、出生時男性の人が女性になる場合は、そういう問題は指摘されていません。これも出生時女性にだけある課題です。
山崎:その非対称性というのは、まさに家父長制だとか家族制度や強制異性愛主義の規範の問題ですよね。フェミニズムがジェンダーという言葉を使ってやろうとしたのは、これらの規範の根底にあるセックス(生物的性、出生時の性)による決定論を批判し、見直すことだと思うのですが、女性学会のジェンダーフリーバッシングへの対応はそれをまた逆に戻してしまったような感じすらします。
吉野:これまで出てきたトランスの言説って、MTFのものが中心なんですよね。テレビに出てくる人でも、女装者はよく見るけど、男装者はあまり見ない。一昔前だと、出生時男性のほうが学歴も高くて、そこそこの社会的立場を得てからトランスをした人がいて、その立場から発言をすると、社会的注目も集まりやすい。いまの50代以上の人では、圧倒的にMTFの言い分のほうが目立ちます。ただ、いまは若い人もどんどん出てきて、FTMの言説も増えてはきています。
あと、トランスしやすさを考えたとき、出生時女性の身体にホルモンを投与したほうが、劇的に効果が出るんですね。筋肉量が増えたり、声変わりしたり、ヒゲが生えたり、男として見なされやすく、パスしやすくなる。FTMの声が顕在化してこなかった背景には、そういう事情もあると思います。トランスバッシングの文脈でも、MTFをどうするかだけが出てきていて、FTMをどうするかという話はあまり出てないですよね。それは、男性の身体と社会が考えているものに対して、あまり注意が払われていないからなんだと思います。男性の性被害もそうですね。
*3 マイクロアグレッション:ありふれた日常のなかにある、ちょっとした言葉や行動や状況であり、意図の有無にかかわらず、特定の人や集団を標的とし、人種、ジェンダー、性的指向、宗教を軽視したり侮辱したりするような、敵意ある否定的な表現のこと。(デラルド・ウィン・スー『日常生活に埋め込まれたマイクロアグレッション』明石書店2020より)
*4 ジェンダーフリーバッシングや「中性人間」については以下を参照:
・飯野由里子『反性差別と「性別二元論」批判を切り離したフェミニズムの失敗を繰り返してはいけない【道徳的保守と性の政治の20年】』2017年10月17日
・風間孝『女性学 / 15 巻 (2008) / 特集「中性人間」とは誰か?―性的マイノリティへの「フォビア」を踏まえた抵抗へ』
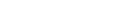


コメント