わかりやすい当事者、ではないところから

——————————————————
日 時:2022年1月21日
聞き手:貴戸理恵、山下耕平、山崎たつお、Lina
——————————————————
山下:昨年、私たちは「ハジコミ」というメディアを立ち上げました。このメディアでは、問題をひとつの当事者性に限定せず、さまざまな文脈がクロスするところの対話を大事にしたいと思っています。今回は、その最初のインタビューになります。吉野さんには、トランスジェンダーの当事者であるとか、性別違和の部分だけではなく、多面的にお話をうかがいたいと思っています。まずは子ども時代のころに感じていたことからうかがいたいと思いますが、いかがでしょう。
吉野:私の場合は、トランスジェンダーのなかでも、性別違和の激しい中核群ではなくて、最初は身体への違和というよりも、ジェンダー規範への違和のほうが早くからあったように思います。子ども時代は、母がイギリスの児童文学が好きだったので、そういう世界観のなかで育ったんですよね。三つ編みのおさげとか、祖母の手づくりのパフスリーブのワンピースとか(笑)。でも、小学校3年生のころから、だんだん活発になってきて、男まさりだと言われたり、きかん気が強いとか言われるようになりました
貴戸:お母さまの好きだった児童文学というのは?
吉野:『ナルニア国物語』や『ゲド戦記』、『指輪物語』、作家で言えばリンドグレーンとかメアリー・ノートンとかアーサー・ランサムとか、児童文学の有名なところは一通りありました。母は、私にもそういう本を読むことを望んでいたんですが、私のほうは、社会問題に興味が向いていって、小学校にあがる前から、『ひろしまのピカ』や『はだしのゲン』を読んでいました。なので、選ぶ語彙や感覚が、まわりとはちょっとズレている感じはあったと思います。
貴戸:吉野さんの時代、ランドセルは赤か黒が主流でしたか?
吉野:そうでしたね。でも、どっちの色もイヤで、買ってもらったのは薄い桜色のランドセルで、それはとても気に入っていました。ただ、習字のカバンは黒のほうがいいと思ってました。それは、男の子になりたいというよりも、おしきせに対する反発のほうが大きかったと思います。
貴戸:おしきせへの反発というのは、親に対する、それとも社会規範に対する?
吉野:両親からジェンダー規範を押しつけられることは、ほとんどなかったです。
貴戸:そうなんですね。どんなご両親だったんでしょう。
吉野:父と母は、もともと東京の出版社に勤めていて、父が本屋を開くために退職して、郷里で書店を開いたんです。
貴戸:どんな本屋さんだったんですか?
吉野:まあ、ふつうの本屋です。母は児童書の本屋にしたかったみたいですが、それでは田舎では生き残っていけない。ただ、エロ本を置くのはイヤだったみたいで、途中から売らない方針になったようです。
山下:そうすると、親から価値観を押しつけられることはあまりなかったけれども、そういうなかで育ってきた問題意識と、学校や友人関係とのあいだにギャップがあったということでしょうか?
吉野:そうですね。ただ、それでいじめられたり、教師からうとんじられるようなことは、あまりなくて、「いろいろ知っているね」という感じで、めずらしがられる感じだったと思います。
貴戸:社会的な問題関心を育てるのって、読書もですが、誰かと対話することで育つ面もあると思います。そういう対話の相手はどうだったんでしょう。
吉野:うちは民放は見ない家で、テレビはNHKだけだったんですよね。なので、家ではニュースの話題とかはあったかな。あと、学校では、小1~小2のときの担任の先生が、私の興味関心を好意的に受けいれて評価してくれていました。
男女別にできている学校
山下:学校という仕組みは基本的に男女別にできていますけれども、ジェンダー規範への違和感は、いつごろから感じていたのでしょう。
吉野:たぶん小学校に入る前から、みんなといっしょではないほうがいい、という思いはあったと思います。なので、ランドセルの色も自分の好きなものにしたかった。学校では、いろんな道具の色が男女別になってますよね。ただ、小学校のときは、服は私服でしたし、自分の好きなものを選ぶことで、そんなに摩擦は起きませんでした。通っていた小学校は、田舎の割にはリベラルな感じがあったと思います。ところが、中学校になると、制服はセーラー服と学ランだし、体育着だとか、持ち物だとか、髪を結ぶゴムの色が決まっていたりだとか、いろんなことが気になり始めました。
山下:それに対して、異議を申し立てたりはしてたんでしょうか?
吉野:小学校時代は、戦争のことだとか、薬害エイズ問題だとか、広く社会に目が向いていたんですが、12歳くらいになると、思春期にさしかかって、外に向いていた目が自分の内面に向くようになったんですよね。そんなときに尾崎豊を聴き始めて、「これだ!」ってなったんです。尾崎は、大人や体制への不信感を表現していた。
山下:なるほど。でも、世代的にはリアルタイムじゃないですよね。
吉野:尾崎が死んだ後ですから、完全に遅れてきた尾崎ファンでしたね。そのころ、三種の神器的に私を構成していたのは、尾崎豊、山田かまち、岡真史の3人で、めちゃくちゃ影響されました。
山下:岡真史さんは、作家の高史明さんの息子さんで、12歳で自殺されたんでしたね。遺された詩は『ぼくは12歳』という本になった。
吉野:そうです。それで、高史明の『生きることの意味』も読んだりして、自分の人生にどういう意義を見いだすのか、猛烈に考え始めたんです。いわゆる第二次反抗期みたいなものが、親には向かずに、すべて社会一般というか、学校の体制などに向かっていったんだと思います。
山下:具体的なアクションは? 夜の校舎で窓ガラスを壊してまわったり、盗んだバイクで走り出したわけではないですよね(笑)。
吉野:中2のときに生徒会の副会長になって、校則を改正しようとしたんです。ただ、ほかに校則を変えようと思って生徒会に入る人なんていなくて、だいたいは内申点が上がると思ってだったり、先生が使いやすそうな生徒をそそのかして立候補させたりで、生徒会長とも、心を開いて話すようなことはまったくなかったんですね。私は、そういう主体性がないのに生徒会をしている人たちを見下していて、なぜ問題意識がないんだと歯がゆく思っていました。
もちろん、思春期特有の自意識過剰だったり、自分を特別な存在と考えていたようなところもあったと思いますが、自分の力で制度を変えてやろうと思っていました。それで、校則のどこから手をつけるか考えたんですが、生徒のあいだでは、持ち物の指定に不満があったんですね。とくに部活の道具などを入れるサブバッグは、高い割には小さいし、すぐ破れるので、不満が大きかった。それを自由化しようと呼びかけました。生徒と保護者にアンケートをとって、こういう意見が集約されたから職員会議にかけてくれと生徒会の顧問に依頼したんです。ところが、その教師はぜんぜん動いてなくて、こちらに適当に返事しているだけで、職員会議で報告すらしていなかったんです。一方では、生徒のほうからも「ぜんぜん進んでない」と言われるし、だんだん獰猛な気持ちになっていきました。ちょうどそのころ、酒鬼薔薇事件(神戸連続児童殺傷事件)が起きて、事件の犯人は同じ14歳で、犯行声明文を読んで、わかるなと思ったところもありました。
貴戸:犯行声明文には「スクールキラー」とも書かれてましたよね。それで、校則改正の動きは、どうなったんでしょう。
吉野:生徒会の顧問がまったく動いてないことを知って、私のなかでストッパーがなくなってしまって、ある朝、顧問の教師をつかまえて、激しい言葉でなじったんですよね。敬語を使うこともなく、一気にまくし立てた。それをきっかけに、教師に対して生徒らしい態度をとるのはやめました。
それでも、もう1回アンケートを実施して、なんとか最後までやるぞと思っていたんですが、ぜんぜん進んでいかないし、生徒のほうも、自分たちの代で恩恵を受けないと意味がないという感じで、すごく短絡的だったので、生徒たちにも失望して、モチベーションを失ってしまったんですね。ガンダムで言ったら、シャア・アズナブルみたいな感じでしょうか。
山下:魂を地球の重力に引かれて自己中心的にしかなれない地球人どもなど滅んでしまえ、みたいな(笑)。
吉野:そうですね(笑)、衆愚嫌悪というか。
山下:大人とか教師に対してだけではなく、同年代に対しても不信感を持ってしまったわけですね。
吉野:いま思えば、最初からすべっていたんです。その学校では、公約を掲げて生徒会活動をすること自体が異例だった。そもそも、そういう土壌がなかった。私が未熟だったこともあって、いろんな人と対話して理解を広めるというやり方もできなかった。生徒たちも、授業を受けて部活をして帰るだけで、運動をつくるような環境ではなかったんだと思います。
それで、だんだん精神的に追いこまれていって、眠れなくなったり、いま思えば軽いうつのような状態だったと思います。そんな状態のなか、中3のときの全校集会でマイクをとって、これまで生徒会はこういう動きをしていたが、顧問が動かずにうまくいかなかったんだと話したんですね。そのようすに、教職員も尋常ではないものを感じてあせったのか、その後、急に対応が進んで、最終的には自由化しようという話になりました。ただ、それは運動が実ったというよりも、私の死にそうなようすに、あわてたんだと思いました。その敗北感のほうが強くて、もうどうでもよくなって、その後、学校に行かなくなりました。
貴戸:そういう吉野さんに対して、親御さんは、どのように?
吉野:親は全面的に自分の味方だったと思います。活動も応援してくれてましたし、学校に行かないことについても、もともとずる休みするようなことはなかったので、そういう性格の人間が行きたくないというなら無理しないほうがいいという感じでした。
山下:学校に行かなくなったあと、教師の対応はどうだったんでしょう?
吉野:教師たちは、まかりまちがって自殺でもされたら困る、という感じだったと思います。私の考えているところを汲んでくれる感じはなかったですね。でも、中学校1年のときの担任とだけは話が通じて、その教師は3年間、家に来てくれていました。
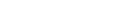


コメント