運動の言葉と時代の変化
貴戸:私は小学校1年生から6年間、学校に行きませんでした。時代でいうと、1985年から1991年のことです。当時の学校の対応は登校強制が中心で、とにかく学校に来るように言われ、それでも行かないと「異常だ」と見なされる雰囲気が強くありました。私の親は、当時の小学校の校長先生から私を地元の子ども医療センターの精神科につれていくように言われてました。でも、私の両親は私を「異常だ」「病気だ」とは思っていなくて、いま思えばありがたいことに、不登校でも問題はないと信じようとしてくれていました。母は当時できたばかりだった東京シューレのことも知っていました。それで、私を地元の精神科ではなく、国府台病院の渡辺位さんのところにつれて行ったんですね。あまり印象深いことは言われなかったようですが。母は地元の不登校の子どもを持つ母親たちとつながり、親の会にも参加していました。そういうなかで私は、不登校・フリースクール運動の言葉に、母親を経由して触れていきました。「不登校の子どもが悪いのではない。問題なのはむしろ学校やこの社会のほうであって、不登校は、そういう問題のある環境に対する子どもの体や心の拒否なんだ、変わるべきは子どもではなく学校なんだ」というようなメッセージですね。具体的な言葉というよりも、態度や関わりに表われるものでした。それが私の自尊心や自信を支えてくれたと思っています。ただ、私自身は、フリースクール的なところやユニークな学校を紹介されてもなじめなくて、行くことはありませんでしたが。とにかく、あるときまでは運動の言葉にすごく救われて、その懐のなかで大きくなった、そのおかげで自尊心を損なわずに育ってきたという実感があります。
しかし、その後大学や大学院で学ぶようになってから、「あれ、おかしいな」と思うことが増えていったんですね。背景には、時代の文脈の変化があります。私が大学生、大学院生だったのは、90年代末から2000年代後半にかけてです。ポスト工業化した社会では雇用が流動化して格差・不平等が顕在化し、学校から仕事へのスムーズな移行が揺らいでいく。そんな議論が日本でもなされるようになったころでした。教育社会学の分野では、苅谷剛彦さんが学力と親の学歴の結びつきを論じていました。ゆとり教育に見られるように、「子どもの主体性を尊重する」という教育の理想が、公教育の領分を切り詰めて家庭に委ねる部分を増やすことで、結果として格差・不平等を拡大させるという現実も見えてきていました。
そうした知識を踏まえると、不登校・フリースクール運動のなかにあった「不登校は子どもの人生の選択のひとつだ、不登校でも問題なく社会に出ていける」という語り口が、危ういものに見えてきたんですね。不登校に否定的な価値が圧倒的で、世間では「不登校だと進学も就職もできない、将来はホームレスになる」とされていたなかで、「不登校でも問題なく社会に出ていける」という主張が意味を持ったことは理解できます。でも、新しい時代状況では、移行そのものが揺らぎ、格差や不平等の問題が出てきてしまっている。「不登校だと社会に出ていけない」に対して「不登校でも問題なく社会に出ていける」というのは、一見対立している主張に見えるけれども、どちらも「ふつうに学校に行っていれば問題なく就職できる」ことが前提になっています。その前提そのものが揺らいでいることを見なければならない、と思いました。
そうでないと、「将来社会に出ていける不登校」だけを肯定して、ひきこもりや無業など「社会に出ていけない不登校」を排除することになってしまう。進学や就労において、家庭の階層格差や劣化した労働市場の問題があることを見過ごすことになってしまいます。また、そもそも、ここで言われている「社会」とは何かを考えないといけませんね。何よりも、一番大事なのは、将来どうなるかはわからないけれども、それでも不登校を受けとめて肯定していくということではないか。そして、それは、親の会やフリースクールなどの現場では、実際になされていたことだったと思うんです。そうであれば、運動的な戦略の言葉だけではなくて、実際になされていることをきちんと言葉にしたほうがいいのではないかと思ったんですね。
私は大学院では、かつて不登校の経験があって、その後を生きている人たちにインタビューしたんですね。そのなかには正規雇用で働いている人もいれば、非正規雇用を渡り歩いている人もいれば、仕事に就いてない人もいました。そのインタビューをもとに修士論文を書いて、そこでは、「不登校でも将来問題なく社会でやっていける」という言い方は、かなり一面的なんじゃないかということを書きました(*1)。
もうひとつ考えていたのは、親の視点から見ると、「子どもが学校に行かなかったけど、社会に出て働くようになりました」というと、そこで物語は完結するんですが、当事者の視点からすると、物語はその後も続いていく、ということです。仕事には就いたけど、きつい職場で、またしんどくなったりもするかもしれない。「就労したらゴール」「高校や大学に入ったらゴール」ではない。運動の物語にはオチがあるけれども、当事者の物語にはその後がある。私が修士論文で言いたかったのは、そういうことですね。
山下:不登校の当事者といっても、親、子ども、経験者ではちがいますし、貴戸さんがおっしゃっていたのは、不登校経験をどう語る(あるいは語ることができない)のかは、その後をどう生きているかによってちがうということでしたよね。そして、親がつくった枠組みのなかに、子どもや経験者の語りがあった。その枠組みにあてはまるものは当事者の声として受けとめられるけれども、あてはまらない語りは、受けとめられてこなかった面がある。たとえば、貴戸さんと共著で『不登校、選んだわけじゃないんだぜ!』(理論社2005)という本を書いた常野雄次郎さんは、東京シューレの出身者ですが、東京シューレの言説には異を唱えていました(この本の常野さんのパートのもとになったのは、不登校新聞での連載でした)。彼が異を唱えた東京シューレの言説というのは、不登校して自分を否定されて苦しかったけれども、フリースクールに出会えて自分を肯定できるようになった、いまは明るく楽しく過ごせていますというような、いわば明るい不登校の物語です。しかし、不登校してフリースクールに通っても、その後に苦しい思いをしている人はたくさんいるのに、そういう存在がなかったかのように明るい不登校の物語が語られているのはおかしい、と言っていました。
しかし、彼の問題提起に対して、不登校新聞でも、きちんとかみ合った議論はできなかったですし、いまにいたるまで、かみ合った議論はできないままです。そして、いまでも不登校・フリースクール運動のなかでは、明るい不登校の物語が語られているところがあります。
——————————————————
*1 この修士論文は2004年に新曜社から『不登校は終わらない』という書籍として刊行された。
不登校〈から〉考える
山下:私自身のことも少しお話ししておきたく思います。私は自分が不登校経験したわけではなく、大学生のときに学生新聞の取材で東京シューレに行ったのがきっかけで、東京シューレのスタッフになって、その後、不登校新聞の創刊時から8年間、編集長をしていました。東京シューレを訪ねて最初に考えさせられたのは、なんで自分は学校に行っていたんだろうということでした。なんで学校に行かない子がいるのか、という問いがひっくり返ったんですね。それが原点です。以後、私は、不登校〈から〉考えるということを基本スタンスにしています。学校に行くことが当然になっていて、不登校が問題化されるような学校の仕組み、社会の仕組みとは何なのか。不登校〈を〉考えるのではなく、不登校〈から〉考えると、いまの社会の仕組みがよく見えてくる。
私は、立場的には「支援者」と言われるかもしれませんが、自分ではそう思ってないんですね。支援というのは、一般的には枠組みや方向がハッキリしていると思うんです。大ざっぱに言えば、いまの社会を前提として、いかに個人をそこに適応できるようにするかが支援ということになっている。しかし、そうではなくて、いまの社会、学校のあり方をどういっしょに考えていけるのか、あるいは変えていけるのか。私は、そこに立とうとしてきたように思います。
不登校経験者が自分の経験を語るというときも、まわりの聞く耳、まなざし、価値観が問われると思います。語りは関係のなかにある。先ほど、親のつくった運動の枠組みのなかでしか当事者の語りが受けとめてこなかったという話をしましたが、フリースクールという枠組みも同じで、その実践に合う語りは受けとめられるけれども、それにそぐわない語りはスルーされるか、もしくは排除されてきたわけですね。あるいは、運動にとって不都合な事実は直視されずにきたところがある(*2)。
また、学校に行かなくても社会でやっていけるという語りは、語っている本人にとっても苦しいのではないかと感じてきたところがあります。学校に行かないことがマイナス視されるなかで、不登校してもがんばっているという姿を見せないと否定されてしまうという構図がある。それは語る本人の問題ではなく、まわりの聞く耳やまなざしの問題です。とくに、マスコミはわかりやすいストーリーを求めるので、マスコミに向けて語られるとき、そういう苦しさが生み出されてきたように思います。けれども、そういう苦しさは語りにくく、抑圧されてきた面があるように思います。
私が模索してきたのは、そういう枠組みに合わせるのではないかたちで、当事者の語ることに聞く耳を持てたり、いっしょに考え合うことができないか、ということだったように思います。
貴戸:「当事者とは誰か」という問いに対して、当事者というのは「立ち去れない人」のことだという捉え方がありますね(中根成寿2010「『私』は『あなた』にわかってほしい」宮内洋・好井裕明編『<当事者>をめぐる社会学』北大路書房)。親には親の当事者性、支援者には支援者の当事者性がある、という言い方もできるけれども、親は「子どもの人生のことなので」と思って関与しないこともできるし、支援者はほかにやることを見つけることできる。しかし、本人だけは立ち去れない。不登校の痛みや不利益があったとき、それが一番ついてまわるのは本人です。でも、逆に、研究者のような周囲の者は去ることができるからこそ、去ることはゆるされないという倫理的な語りもあります(天田城介2010「底に触れている者たちは声を失い、声を与える」宮内・好井編、同上)。今日、あらためてお話をうかがっていて、山下さんのあり方には、そういう倫理を感じるところがあります。当事者も、ずっとそこにいるのはしんどいので、自分の問題から目をそむけて、どこかに行ったりもしますよね。でも、そういうときであっても、その問題から目を背けてはいけないというような倫理……。
山下:そうかもしれません。私は自分を当事者だとは思っていませんが、当事者性のある場に立ち続けてきた。ただ、それは頭で考えてやっていることではないんですよね。かかわりのなかで、結果としてそうなっているというのが、正直なところかなと思います。最初からそういう倫理観をもってやってきたということではない。
——————————————————
*2 たとえば、東京シューレでは過去に性暴力事件が起きていたことが被害者の提訴で明らかになった。裁判は和解したが、事件当時の対応、提訴後、和解後の対応などには疑問が残されている。
閉じる物語、閉じない語り
貴戸:明るい不登校の物語が、聞き手の枠組みから外れるものを排除して成り立っているというのは、私もその通りだと思います。しかし、それは物語というものの宿命でもあると思うんですね。人は語りを通じて、自分自身や世の中を把握していくわけですが、すべてを語り尽くせるわけではありません。物語は閉じた小宇宙をつくって、ノイズを「語りえないもの」として排除することで、初めて理解できるものになる。意味のまとまりができて、人に手渡せるものになるということがある。
不登校に対して、世間の理解がほとんどない状況にあって、不登校でも社会に出ていけるという物語を生み出して、それを人に伝わる言葉にして差し出したことの意義は、たいへん大きかったと思います。おそらく語り手たちも、それで自分の体験がぜんぶ語り尽くせると思っていたわけではなくて、そのことで不登校への偏見を変えていくことができるなら、その一助になればという気持ちで語っていたのではないかと思います。
でも、その当事者の語りにも、その後があって、閉じられた小宇宙だけで、自己を語り続けることはできないわけですね。そこから漏れ落ちたものをすくいとって、また次の物語を語っていくことが必要になる。そうすると、また、そこから漏れ落ちるものがある。だから常に新しい物語が必要とされつづける
閉じた小宇宙をその都度つくって語ることがひとつの戦略だとすれば、もうひとつの戦略は、物語にしない、閉じないということですよね。宙ぶらりんで、矛盾をはらんだまま、誰に通じるかわからないけれども、自分の状態を言葉にしていく。たとえば、づら研は後者に近いことをやっているのかなと思います。閉じたものから漏れ落ちるような語りを扱っているような感じがする。もちろんそこには課題もあって、語りが閉じないということは、何を語っているのかわからなくなったり、人に通じにくいなどしんどい面もあると思います。でも、わかりやすさよりもノイズを排除しないことを優先させるという心意気はあるのかなと思います。
山下:そうですね。そういうことを延々とやっている。考えてみたら、づら研も始めて10年になりますね。
貴戸:始めたのは2011年6月でした。
山下:参加者の人からは、「ここに来ていても何の解決にもならない」と言われることもありますね。参加していても生きづらさが解消されないではないか、と。たしかに、解消しようという発想があまりない。解消するという目的で直線的に進むのではなくて、延々とエンドレスにグルグルと話し合っている感じがある。でも、それが大事なことではないかと思っているんですよね。ただ、一方で、づら研も、正式名称が「生きづらさからの当事者研究会」であるように、自分たちの感じている生きづらさから、そう感じさせている社会のあり方を問うというスタンスはあるように思います。この社会のなかで、いかに自分の内面をコントロールしてうまくやっていくか、ということではなく、自分の感じている不調和からこそ、この社会や、自分のまわりの関係を問い直していく。また、特定の診断名や障害名に当事者性を置くのではなく、つまりは名づけによって切断するのではなく、生きづらいという動詞に当事者性を置いている。そういう意味では、とてもあいまいな当事者性で、さまざまな当事者性が持ち寄られる。もちろん、その限界もあるわけですが……。
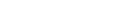



コメント