「発達」とは?
山下:自分が問い直されることによって初めて、本当の意味で他者と出会うことになるわけですね。それはご著書で書かれていた「『発達』というのは『異なる他者』との出会いである」というテーマともつながっていくように思います。
野田:野崎さんの書かれている「発達」の概念は、階段を昇っていく、パワーアップしていく発達のイメージとはまったくちがうんですね。
野崎:いまの社会では、個人の能力を高めて自己決定をして生きていけることがよいこととされていて、教育もそういうものになっている。しかし、そこへ向かう「発達」とは異なる「発達」があるのではないか。
大事なことは誰か賢い人が考えていて、導いてくれるように思わされている。たとえば「誰かが原発をなんとかしてくれる」と思って、誰も責任を取らない。そんな社会があるからこそ、人を信じるとか、ともに生きるということの中身が奪われている。そのなかで、私たちはいかに人間関係なり社会のあり方なりを編み直すことができるのだろうか。そういう立場に立てば、「正しい発達」とか「発達段階」ということではなくて、人が何かを知ろうとすることには、「発達」があるんだと思います。
小林:青い芝の会が「他人の力を借りなければいけないことをプラスに捉える」というのと、野崎さんのおっしゃる「発達」は、つながっているように思いました。
野田:私がとくに胸に刺さったのは「他者というのは、自分に対して問いかけてくる存在である」「その問いかけに対して、『答えるか、答えないか』を選ぶ責任が私たちにはある」というくだりでした。この言葉は哲学的なようでいて、実はとても肌で感じるものだと思います。実際に生身の人と出会って、その人の存在や背景を知っていけばいくほど、肌にざわざわって来る感じがする。
山下:たしかに、一般的な意味で「発達」している人は、わざわざめんどくさい関係を結ばなくても生きていける社会になっていて、むしろ排除されている人のほうが、他者と出会わざるを得ないなかで、野崎さんのおっしゃる「発達」に開かれていくチャンスを持っているのかもしれませんね。
野崎:そうですね。障害を持っている人は、自力では生活できないがゆえにネットワークを持たざるを得ないところがあります。そしてそのネットワークは、たとえば阪神大震災のときに、すごく活きたんです。震災の際、僕の知り合いの障害者はどうしたかというと、それまであったネットワークを使って、ふだんのたまり場に集結した。そこに関係者がやってきて、物資の調達がはかられたり、人手が足りないところへ駆けつけたりした。翌朝から私たちは炊き出しを始めて、近所のみなさんにふるまいました。そのとき、ふだん考えられている障害者と健常者の強さと弱さが逆転していたんですね。障害者はふだん助けられてるから弱い存在なのではなくて、助けを得た者が他の人を助ければ、輪になっていける。それは、もともとのネットワークがあったからこそ、できたことでした。
山下:個人が自分の力で生活できると思っているのは、マーケットに依存しているからで、マーケットがマヒしたときにはすごく弱いですよね。
野崎:たとえば災害時に避難所となる学校の校舎って、まったくバリアフリーが進んでいないですから、身体障害や高齢者の人には使いづらかった。あるいは配給が来たときも、音声言語で通達するんで耳が聞こえない人には通じなかった。同じ避難所の精神障害のある人は「明日からの薬がない。困った」と言っていました。知的障害のある人は、避難所で奇声をあげてしまったりして、「家があるんだったら半壊でも帰りなさい」と言われたり、すごい差別にあったという話を聞きます。そうしたことを考えると、地域にたまり場のような場所をたくさんつくっていく必要があるなと思います。
「発達」と「いること」の価値
山下:学校についても、「障害児を普通学校へ」という運動がある一方で、不登校している人たちがいる。学校の能力主義的な思想は問われないまま「普通学校へ」としても、それは本当の意味では受けいれたことにはならないですよね。ただ、個人の能力を伸ばすことのよい面もあるかと思います。たとえば野崎さんは、自分が歩けるようになったことに対して、どういう思いがありますでしょうか?
野崎:歩けて便利だなとは思います。ただ、それは便利なだけなんですよね。多少不便であっても、車椅子に乗ったり、あるいは人におぶってもらったりして、行きたいところに行けるはずなんです。歩けたら幸せかというと、そうではない。便利さは必ずしも幸せにはつながらない。
山下:その通りだと思いますが、少し踏み込ませてください。野崎さんは身体に障害はあったけれども、知的な障害はともなっていなかった。そのことと、大学で自らの関係世界を広げていくことができたのは、おそらく無関係ではない。一方で、知的障害のゆえに親元に留め置かれている当事者も多くいることと思います。そのような方々の「学び」や「発達」を野崎さんはどのように考えていらっしゃいますか。
野崎:知的障害の方と一口に言ってもいろいろですが、いわゆる「発達」が見込めない、最重度の知的障害の方と接してきて思うのは、本人の楽しみを広げることが一番だということです。たとえば、すごく琉球民謡が好きな方がいらっしゃったんですが、その方は身体にも障害があったので、自分でカセットテープをセットできないんですけれど、こちらがセットしたら、笑っているなと取れる反応をされる。それで「この人はこういうのが楽しいのかな」とわかる。それはやっぱり地域で暮らしているからわかるんだなと思います。施設で用意されたメニューをこなすだけだったら、あんなふうに笑顔を見せることはないように思います。それは、こちら側の勝手な思い込みではあるんですけれど、その思い込みに賭けるしかない。本当に支援というものの原理的な部分を考えるとするならば、そこに賭けていくしかないと思います。
山下:言語以前のところでのコミュニケーションですよね。たとえば、赤ん坊との付き合いにもそういう部分があるなと感じます。赤ん坊がいることによって、まわりの関係のあり方の幅が広がっていく。自分ではできないことが多いからこそ、逆にその人が「いる」ことの価値がわかるようなことは、あるように思いますね。
野崎:澤田隆司さん(*2)は、ある知的障害の方が施設に入るかという話が出たとき、「じゃあ俺といっしょに住まんか」って言われたんですね。それをサポートするまわりも大変なんですが、澤田さんはにんまりと笑ってはりました。地域でともにあることへの賭けが、そこにはあると思います。
野田:それは祈りに近いように感じますね……。
野崎:社会は「することの価値」に偏る一方ですが、いかに「いることの価値」にもっと目を向けられるかというのは、重要なテーマだと思います。
山下:生の無条件肯定につながりますね。この部分が大事にされてないと生きていけないけれど、いまの社会では「そんなこと言っているのは甘えだ」と叩かれてしまいますよね。
野崎:「することの価値」を否定しているわけではなくて、「すること」以前に「いること」がある。
小林:大学のときの先輩で、下半身に障害を持ちながらひとり暮らしされていた人がいたんですが、僕はその人に対して表面的なことしかできなくて、「他者」として出会えてなかったように思います。そういう自分を価値が劣るものとしてまなざされたらイヤだなとも思ったんですが、「発達」というのはそういうものではないんでしょうか?
野崎:私が言っている「発達」というのは「それができたからいい・できないから悪い」というものではなくて、そういう「評価」をことごとく拒むものとしてあると思っています。そこに点数はつけられないですよね。逆にいうと、今の社会では「発達」がいかに評価主義に毒されているか、ということの裏返しだと思います。
———————————————
*2 澤田隆司さん:「青い芝の会」兵庫支部会長を務めるなど、バリアフリーが進んでいなかった時代に障害者運動を中心的に担ってきた。2013年10月に他界。
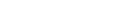



コメント