ずっと“学園祭前”のような高校時代
貴戸:進学はどうされたんでしょう?
吉野:いろいろ考えて、一番リベラルな高校を目指しました。旧制中学の高校ですね。服装も自由で校則もほとんどない。ただ、一番の進学校なので、合格するには厳しい状況でしたが、どうにかすべりこんだ感じでした。
山下:高校はどんな感じだったんですか?
吉野:中学とはまったくちがって、県のいろんなところから生徒が集まっているし、いじめをするような人はいないし、社会的関心のある人も多かったですね。それで、ものすごく楽になりました。
山下:対話ができるようになった。
吉野:そうなんです。入学直後の生徒会のオリエンテーションで、70年代の生徒総会の制服自由化の議論を録音したものを聞かされて、当時の高校生が「我々は人から与えられた自由を喜ぶような人間になってはいけないんだ!」とか話してるんですね。そうそう、こういうことがやりたかったんだ、と。それで、入学式の直後に生徒会室に行って、高校3年間は生徒会活動に全力を注ぎました。
山下:学校のなかで具体的に変えようとしたことは、どんなことだったんでしょう?
吉野:学校を変えるとか社会問題に対してアクションするというよりは、すべてを主体的に自分たちの力でやろうということでしたね。そもそも、学校行事についても、教職員と生徒の代表で、日程から何から決めていたんですね。行事の内容は、教師の介入なしに生徒で決めて実施する。そういう活動を3年間やりきった感じでした。
山下:なるほど、中学のときは上から決められていることに対して、それを変えたいということだったけれども、高校はもともと自治的で、生徒が主体的に決めていけるから、それが楽しかったということですかね。
吉野:学園祭の前が一番楽しいという感覚に近いかなと思います。高校は3年間、ずっとそういう感じでした。
山下:ジェンダー規範への違和感は中学ぐらいから感じていたということでしたが、そのあたりは高校ではどうだったんでしょう?
吉野:高校は私服で通えたので、制服の悩みとかはなかったんですね。ただ、人間関係では悩むこともありました。私はハッキリとものを言って、すべての人と対等にわたりあっているつもりだったんですが、何かのきっかけで、私の体型のことを男子生徒が話題にしているのを知ってしまったんですね。それで、対等に思っているのはこっちだけなのかなと。こちらは、男子生徒に対して「あいつは肩幅が広くてテストステロン値が高そう」とか評価することはないのに、「胸が大きい」とか「いいカラダをしている」とか、こちらの体型を一方的に評価されるというのはフェアではない。それは、知りたくないことでしたし、ほんとうにイヤで、苦痛でした。
あと、生徒会が楽しかったので、恋愛への興味はそんなになかったんですけど、男の子から告白されたことがあって、つきあってみたこともあったんですね。それで、ふたりで出かけると、男性と女性のカップルとして町の人に見なされることを意識してしまって、これは無理だなという意識が高まったんです。「つきあっている」と見なされることも苦痛だったし、性別で見なされるのがイヤなこともハッキリとわかりました。中学のころから、ちょっと男の子といっしょに帰ったりするだけで、「つきあっている」とからかわれることがあって、そういうのがものすごくイヤだったんですが、当時は、それが関係性を他人に規定されることがイヤなのか、女役割を担わされているのがイヤなのか、混ざり合っていたように思います。それが高校に入って、男の子とつきあってみたことで、ハッキリとしたんだと思います。女役割を担わされるのは無理だなって。
貴戸:女役割を担わされるのが無理というのは、女性であるということ自体への違和感と、女性として気遣いを求められるとか、かわいらしい格好を求められるとかいうことへの違和感があって、重なりながらもズレるところがあると思いますが、そのあたりはどうなんでしょう。
吉野:リベラルな高校だったので、まちがっても「もうちょっと女らしい格好をしろ」と言われるようなことはなかったんですが、自分がどんな格好をしていても、どんなふるまいをしていても、否応なしに女と見なされる、それがこの先もずっと続くのかと思ったら、それは無理だなと。
私の場合、トランスジェンダーといっても、「子どものころは、いつかペニスが生えてくると思っていた」とか、「生理が来たときにイヤすぎて泣いた」とか、そういう典型的なエピソードがないので、常に正当性を疑われ続けてきたんですね。身体への忌避感とジェンダー役割への忌避感とは、厳密に腑分けできないところがあります。大学に入ると同時に、胸をつぶして生活し始めて、その以前から胸がイヤだという気持ちはあったんですけど、それは女の身体だからイヤなのか、胸がふくらんだ身体だからイヤなのかというと、そこも腑分けは難しいです。ただ、「この身体が自分にはフィットしない感覚」と言うほうが正確で、「女の身体だからイヤだ」と言うのはしっくりこないように思います。
貴戸:ご著書(『誰かの理想は生きられはしない:とり残された者のためのトランスジェンダー史』青土者2020)で、子宮に対する違和感はさほどないけど、胸に対する違和感はあるという記述があって、なるほど、そこは切り離して考え得るんだということが新鮮でした。
吉野:トランスジェンダーのなかで、わりと身体への違和感の強いタイプの当事者の人でも、子宮・卵巣と折り合いをつけられる人はそこそこいるんですよね。だって、子宮とか卵巣って見えないじゃないですか。ホルモン治療を受けて生理さえ止まっていれば、子宮・卵巣を意識して過ごすことはない。なので、子宮・卵巣がイヤだというのは、医療のストーリーが入ってきて、言わされている面もあるのかなとも思います。
貴戸:性別違和がないシスジェンダーの女性であっても、生理がうざいからピルを飲んで緩和するという人もいるので、そのあたりは連続性もあるのかもしれないですね。
吉野:そうかもしれないですね。

性同一性障害とトランスジェンダー
山下:ご著書を拝読して、性同一性障害とトランスジェンダーのちがいが、こんなにも大きい問題なんだと初めて知りました。また、トランスジェンダーと一口に言っても、人によって、いろいろ異なるわけですね。そのあたりをお聞かせいただけますでしょうか。
吉野:女性役割を担わされることへの不快が何なのか、知ろうと思っても、当時は身近にインターネットがなかったし、知る手段もなかったんですよね。そんななか、私が高校生のころ、98年に日本でも正規医療が始まって、それをニュースで知りました。どうやら性別適合手術ができることになったらしいと。でも、当時は、いわゆる闇、非正規の美容整形外科や海外での手術が多くて、情報も手に入らなかったし、麻酔医がいないらしいとか、入院施設がないとか聞くと、ちょっと不安だなと思ってました。実際に死亡事故もありましたしね。
なので、性同一性障害と診断されて、正規医療の大学病院で手術を受けるルートのほうが安心できるかなと思って、大学1回生、18歳のときにジェンダークリニックに行ってみました。私の場合、それまで性別に関する違和感について、自分のなかに名づけや概念を発見していなかったので、性同一性障害を使って手術をしようということに対して、政治性とか意味づけを見いだしていなかったんですね。たんなるルートとしてしか考えていなかった。そこにどういう闘いがあったのかまで、思いがいたってなかったんです。しかし、自分で勉強を進めるにつれて、2003年に成立した性同一性障害特例法(性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律)には、戸籍を変えたかったら結婚するなとか、子どもを持つなとか、生殖腺を切れとか、外性器の手術をしろといった要件があって、さまざまな問題があることに気づいていきました。
山下:自分の状態に名づけはないけれども、性同一性障害という枠組みに近づいたら、これはちがうと気づいていったわけですね。
吉野:ジェンダークリニックに通い始めたころは、性同一性障害という名前は、手術を受けるために必要な診断として、それ以上は何も思っていなかったんですけど、その後、自分を説明する言葉としては採用しなくなっていって、20歳くらいからは、トランスジェンダーもしくはクィアという言葉を使っていたと思います。
山下:性同一性障害とトランスジェンダーのちがいを確認したいのですが、性同一性障害(Gender Identity Disorder)は、男女の区分を前提としたうえで、出生時の性と性自認が異なっているということで、トランスジェンダーは、男女の区分にかぎらず、出生時の性に違和感があるという理解でよいでしょうか?
吉野:基本的には、医学的な診断名である性同一性障害もトランスジェンダーに内包されています。出生時の性別とはちがう性別で生活している、生活したいと思っている人というところでは、同じです。ガイドラインで言ったら、性同一性障害は出生時の性になじめず、逆の性に対する持続的な同一感があるということです。いわゆる正規医療の介入を必要としなければ、診断を受けずにトランスジェンダーと名乗ってやっていく人もいます。ただ、男女の区分を支持していない当事者であっても、外科医療が必要ならば診断を受けることもありますし、厳密に分けられるものではないです。
貴戸:吉野さんがトランスジェンダーという言葉と出会った経緯は?
吉野:関連図書を読みあさっていて、海外での一般的な言い方はトランスジェンダーなんだと知りました。トランスジェンダーという言葉は、いまは包括的な言葉として使われていますが、当時は、性別違和の強さに応じて、トランスセクシュアル、トランスジェンダー、トランスヴェスタイト(異性装)みたいな使い分けがされている時代でしたね。
貴戸:トランスジェンダーという言葉に出会ったとき、自分のことを説明した言葉だというような実感があったんですか?
吉野:そんなに、すごくフィットしたという感じではなかったですが、性同一性障害については、「障害」というのはどうなのかという思いはあったので、こっちかなという感じでした。当時は、「金八先生」(*1)の影響で、性同一性障害がブームのようになっていたので、性同一性障害で説明したほうが早かった。大学自治会でユニバーサルトイレを設置しろとか、通称名の学生証を出せという話を始めたときも、性同一性障害のほうが通りがよかった。なので、最初は便利使いをしていた時期がありました。
*1 「3年B組金八先生」第6シリーズ(2001年10月~2002年3月)で、性同一性障害の生徒を上戸彩が演じた。小山内美江子。
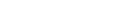


コメント