ニーズを持つのが当事者?
野田:上野千鶴子さんが、人はニーズを持ったときに当事者になると言っていることに引っかかりました。ニーズがハッキリしていたり、自分はニーズを持っていると言える人はいいけれども、私の実感からすると、当事者というのは、そういうところからも、こぼれてしまうものです。友人など、混乱状態の渦中にある人から相談を受けることもありますが、いま渦中にいてつらそうだという人は、ニーズをきちんと立ち上げるにいたっていないように思えるんですね。私自身も、これが私のニーズだとハッキリ言えるようなものは、居場所やづら研にかかわるなかで、時間をかけて獲得してきたように思います。
いま、私は就労支援のB型作業所にも行っているんですが、その場ごとに、ある程度、自分をカスタマイズできる感覚はあります。居場所にしても、作業所にしても、自分をすべて同一化できることはないけど、この場では自分のここは開けるけど、ここはちがうということがある。
ニーズが明確になっている当事者というのは、はたから見てわかりやすく望ましいんだろうけど、そこに自分がハマってしまうことへの抵抗感もあります。ハッキリしたニーズからはこぼれ落ちてしまうものがあって、そこで苦しんでいるものがある。ニーズはあるんだけど、それが何かわからないもやもや感と、ニーズを当事者として語ることが期待されることと、そのギャップにどう向き合っていくか。そのあたりをどう考えたらいいんだろうと思いました。
柳:私も上野さんの当事者の定義には違和感があります。私自身も、当事者になる、選んでなったと思ったことは一度もないです。自分で構築したとか、ニーズが最初からあるという感覚もない。でも、当事者だとは思っています。なので、当事者に強い個人が想定されていることには違和感がありますが、一方で、使える概念だというのはわかります。ニーズというのは、野田さんが言うように、居場所だとか、他者との関係のなかで生まれたり気づいたりするものだと思います。そういう関係のなかで、それまでは抑圧されていて気づけないものが出てきたりするんじゃないでしょうか。
少し前に自己責任という概念の歴史を調べたんですが、自己責任という言葉は、どうやら90年代半ばから一般的に使われ始めたようなんですね。もともとは市場用語で、企業と株主のあいだで使われているものだった。それが、だんだん広く個人の問題として使われるようになった。日本では、90年代半ばごろから、自由とか選択とか自己決定とか、個人が前に出てくるようになった。それと、当事者概念が出てきたこととは、何かつながっているような気がします。しかし、当事者という概念が自己責任論みたいになるのはイヤだと思ってるんですね。自分で主体的に自己決定するなんて、ほんとうにそんなこと可能なのか、わからない。能動的にやっていくことは大事だとは思いますが、自己責任論に通じるこわさも感じました。
それと、山下さんが、それぞれの当事者は同じ社会構造のなかで苦しんでいるのであって、個別の問題もあるけど、共通の問題もあるということを言ってましたね。連帯の可能性というか。でも、一方で、たとえば階級問題を前面に出すと、性差別など別の共通の問題もかすれてしまうという批判もあります。そのあたりはどう思っているんでしょう。ひとつの当事者性で固まってしまうしんどさは、たしかにあると思いますが、それは理念としては言えても、アイデンティティを相対化できるような具体的な土台となる足場があるのか。これから始めようとしているハジコミが、そのきっかけになるとよいのだとは思いますが。
貴戸:クリアなニーズが見えないところの当事者性みたいなものがあるというのは、私もそう思っています。一方で、上野さんは、「(非当事者と区別して当事者を優先させることに)認識利得があるなら当事者という言葉を使えばいい」と言っているわけですね。では、不登校・フリースクール運動に即してどうかと言えば、90年代前半までは、認識利得はあったと思います。学校に行かない子どもの当事者性を強く打ち出して、非当事者である学校の先生や専門家が、学校には行くべきだと決めつけてくることを跳ね返していった。けれども、90年代後半以降、非正規雇用や不安定雇用が増えていって、ひきこもりの問題も立ちあらわれてきたりするなかで、そういう認識利得は揺らいでいったように思います。
熊谷晋一郎さん(小児科医)は、『当事者研究――等身大の〈わたし〉の発見と回復』(岩波書店2020)という本のなかで、当事者研究という営みは、当事者運動から出てきたものだが、当事者研究には当事者運動とはちがう背景があると言っています。当事者研究では、当事者運動のように社会を変えるために言葉をつむぐわけではなくて、いま自分がどう生きているか、どうまわりの世界を観ているか、生活世界のリアリティを記述していくことが主題になっていると言うんですね。運動というのは、敵を立ててそれと闘っていく、壁を壊していくという面がある。それに対して、当事者研究はコミュニティ志向で、専門家とも協力関係をつむぎながら、本人が居心地のよいように生活を変えていこうとする。べてるの家でも、「偏見差別大歓迎」というキャッチフレーズを打ち出している。それは、偏見や差別を告発するという運動とは一線を画すものですね。調和重視なところがある。
その背景には、自己決定の主体みたいなものの輪郭がぼやけていて、自分のニーズが何かを自分ひとりで決められるような世の中ではなくなってきている、ということがあります。自分とは何なのか、自分のニーズが何かということを見いだすには仲間や共同性が必要で、でももうそれは当たり前に存在するものではなくて、共同性からつくっていかなければならないような時代背景がある。そうしたなかで、自己や自分のニーズを生み出す関係構築の過程が重視されるようになっている。そういう背景を考え合わせると、生きづらさという文脈においては、当事者という言葉の賞味期限は切れかかっていると思います。ただ、必要とされる文脈もあるので、認識利得があるかぎりでは、戦略的に使っていくことはあり得ると思っています。
柳さんがおっしゃっていた、90年代以降、個人が前景化し自己責任が問われるようになるのと同時に、主体性が言われるようになったというのも、たしかにそうだと思います。たとえば不登校フリースクール運動でも、フェミニズムでも、当事者主権は市場に親和的なところがあって、サクセスストーリーにとりこまれやすい側面がある。そこで、当事者の声を社会に届けるというスタンスを保ったまま、個人的にの成功してイチヌケを目指すのではなく、いかに共同性の側に立って、他者とつながりと手をたずさえ続けることができるか。それは、現場の実践と、それをどう記述していくかの両面から問われていることだと思います。
山下:不登校にしても、生きづらさにしても、混沌としてハッキリと言葉にならないものだと思うんですよね。先ほど、私自身の立ち位置みたいな話をしましたが、私が自分のことを「支援者」とは思えないのは、私がかかわってきたなかでは、当事者にはこういうニーズがあるので、こういう方向に向かって支援しましょうというような簡単な話ではないと感じてきたからです。「支援者」側があらかじめ持っている枠組みでもって当事者とかかわることがいかにおこがましいか、不登校とかかわり始めた当初に思い知らされたところがありました。それは、渡辺位さんの影響もあったと思います。こちらの枠組みで接しているだけでは、人とつきあったり、場をともにすることにはならない。
それと、柳さんのおたずねにあった、階級問題と性差別の問題について。たしかに、そういう矛盾は常にあると思います。たとえばフェミニズムでは、「女性」とひとくくりに言っても、そこに階級差や人種問題があることが批判されてきたわけですし、どう切り取っても矛盾はあるのだと思います。日本の社会運動では、70年代以降、個別の当事者が社会に問題を訴えることが多かったように思います。しかし、それでは階級などの構造問題は問えず、ややもすれば、いまの社会構造のなかでいかに当事者が認められるか、という構図になる。一方で、同じ階級のなかでも、個別の当事者の置かれている問題はちがっている。難しいですが、個別の文脈を大事にしながら、しかし対立する点などはあいまいにせず、別の文脈にある当事者とも社会のあり方をいっしょに考え合う場をつくっていきたいと思っています。ただ、おっしゃるとおり、現段階では観念的なので、具体的には、今後、ハジコミを進めていくなかで、そういう対話の場をつくっていきたいと思っています。
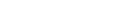



コメント