「内向的」であることは認められなかった
それと関連して、5年ほど前から韓国の若者のあいだですごく話題になっているMBTI(性格診断テスト)があります。MBTIが流行りだしてから、突然、韓国の人たちが、自分は内向的か外向的かを気にし始めたんです。それはとても印象的でした。韓国では長いあいだ、外向的な人が「ふつう」で「正しい」とされてきたんです。内向的な人というのは、存在しないか、存在してはいけないような雰囲気でした。でも、いまでは少なくとも半分以上の人が「私は内向的だから理解してほしい」と言えるようになっています。逆に、外向的な人が「私は外向的すぎるので、あなたを不快にさせるかもしれません」と配慮するような場面も増えました。
個人だけではなくて、その社会によって、外向性・内向性の社会的な平均値みたいなものもあるように、私は感じています。たとえば、中国、韓国、日本の3カ国を比べると、一番外向的なのは中国人、次に韓国人、一番内向的なのは日本人だと思います。日本人が韓国人に会うと「うるさい」「疲れる」と感じることがある。でも、韓国人も中国人に会うと同じように「疲れる」と言うんです(笑)。
日本でも、たとえば戦時中は全体主義的な社会だったこともあり、外向的な人が「ふつう」とされていた時代があったかもしれないですね。でも、1980年代ごろには、内向的な人も認められるような雰囲気が出てきたんじゃないでしょうか。一方で、韓国で「隠遁型青少年」があらわれ始めたころは、内向的な存在自体が認められていなかったんです。それゆえに、そういう人たちの存在が見えにくくなっていたと思います。
でも、韓国でも最近ようやく「そういう人たちもいるよね」と気づき始めているような気がします。これは私自身の経験から感じていることで、かならずしも証明された事実ではありませんが。
私が「隠遁」「孤立」について深く関心を持つようになったのは、2005年ごろのことです。きっかけは、親しい友人が隠遁・孤立状態になったことでした。当時、韓国には、そういう人を支援するためのノウハウも、議論も、何も存在していなかったんです。そういう時代状況のなかで、「ユジャサロン」の活動を2010年から始めたんです。
民間のカウンセラーや精神科医がこの分野に関心を持つことはあっても、公的な基盤で青少年とともに孤立を支援するような取り組みは、それまでなかったんです。韓国で政策的な支援が始まったのは、実質的には2010年代の終わりごろからです。
私たち全員が「ニート」?
ある意味、日本のほうが韓国よりも近代化がずっと早く進んだので、個人という概念が先に社会に登場したのだと思います。個人という概念があって、初めて孤立という問題が出てきます。伝統的なコミュニティや大家族のなかでは、個人であることが難しく、孤立という状態も存在しにくい。
また、個人というものが社会にあらわれてからバブル崩壊の時期まで、日本のほうが韓国よりも少し長かったんです。そのぶん、日本より韓国のほうが坂道を転げ落ちるスピードが速かったのではないかと思います。韓国では、こうした心の状態を理解するために、「ガンダム」や「エヴァンゲリオン」をよく参考にしています。日本ではあまり特別視されないかもしれませんが、韓国ではとても注目されています。
おそらく、韓国で隠遁・孤立について社会学的に本格的に扱った最初の本は、2018年に私が書いた『비노동사회를 사는 청년, 니트(非労働社会を生きる若者、ニート)』だと思います。ソウル研究院(ソウル市の政策を研究する機関)から依頼されて書いたもので、私は社会学の博士号も持っていないのですが、ほかに頼める人がいないということでした。
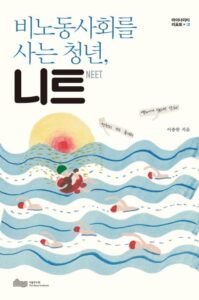
この本では、労働市場の変化や雇用構造の変化と「ニート」の問題を結びつけて考えようとしました。日本や韓国は、労働を非常に重視して、労働が存在理由になってきた社会だったからこそ、逆に「非労働的な人々」が多く生まれてしまったのではないかと考えました。
また、日本や韓国に共通する特徴として、欧米社会が「規律社会」から「成果社会」に移行したのに対して、日本や韓国では、一方では規律型の権威主義が残っていて、なおかつ自発的に搾取される成果主義にも適応しないといけないという、二重の困難があると思います。
日本や韓国では、「ひきこもり」「隠遁」の問題を解決するには就職させるしかないと考えられがちです。しかし、もしこの問題が社会の雇用構造の矛盾から生まれているなら、「雇用させること」で解決しようとするのは矛盾しています。だからこそ、「働かない人は社会の一員になる価値がない」と考える風潮をあらため、存在の意義や価値が労働ではなく、存在そのものであることができる社会にならなければ、回復にはつながらないのではないかと思います。
しかし、日本でこうした話が受けいれられるのか私にはわかりませんし、韓国では確実に受けいれられていません。こうした話をすると「社会主義者」とレッテルを貼られてしまいます。ですが、AIやロボットなどの技術進展を考えると、これからは「脱・雇用経済」に向かっていると私は考えています。実際、私たち全員が、これからはむしろ「ニート」に近い存在になっていくのではないでしょうか。だからこそ、問題をもっと広く捉え直す必要があると思っています。
「変な人たち」ではない
孤立のメカニズムについて、もう少しちがう角度で考えてみたいと思います。孤立という状態をどう捉えるべきか、そこに視点のちがいがあると思います。
私は最初、「隠遁青少年」「孤立青少年」という捉え方に異議を唱えたくて、「隠遁」「孤立」「ニート」は主体ではなく、状態にすぎないと言ってきました。そういう「変な人たち」がいるのではなく、誰でもその状態になれば困難を感じるものだと捉えるべきだと思ってきました。私の主張が実際の政策に影響を与えられたかはわかりませんが、少なくとも韓国の政策研究者たちは「これは状態である」ということに、ある程度同意し始めているように思います。でも、それは研究者だけで、一般の人々は依然として「変な人たち」と思っているでしょう。
しかし最近は、「孤立状態」以前に「孤立感」を感じた時点で、すでに支援が必要なのではないかと考え始めました。社会的には活動しているけど、内面は孤立している、そういう人たちもいます。また、韓国では、過度なプレッシャーにさらされて、燃え尽きてしまい、孤立状態に陥る人も多い。私はそれを「燃え尽き型ニート」と呼んでいます。外から見れば、何も努力していないように見えるかもしれませんが、実はものすごく努力している。
あるいは「間欠型ニート」という概念も使っています。ニートの時期と就労している時期を繰り返す人たちのことです。日本にも間欠的なニートやひきこもりはいるでしょうし、韓国にも継続的なニートやひきこもりはいますが、韓国ではこの「往ったり来たり」している人の割合が、日本よりもずっと多いように思います。
孤立感はどこから
なぜ若者が孤立してしまうのかを考えるとき、私は2011年にその原因を3つにまとめて考えていました。
1つ目は「社会的な衝撃によってレールから外れること」で、たとえば、いじめや暴力を受けて、学校を辞めざるを得なかったり、進路を変更することですね。
2つ目は「家庭内の継続的なストレス」で、親からの期待の高さや過剰な管理があったり、あるいは家族が解体していることです。
3つ目は「もともとの内向的な性格や傾向」で、憂鬱/躁鬱傾向、完璧主義、対人関係スキルの問題などです。
これらが徐々に積み重なって、孤立状態になるのだと思います。ほとんどの場合、この3つをすべて持っているように見えます。日本でも、この3つのうち1つか2つを持っている場合が多いのではないでしょうか。でも、2つ目の「家族」において支えがしっかりしていると、孤立に陥らずに済むことも多いと思います。
「孤立」とは、たんに家に閉じこもって出てこない人だけを指すのではなく、もう少し概念的な「孤立感」として捉えたほうがよいと思います。韓国も日本も先進国ですが、両国の若者たちは「食べて生きていくこと」に対して、実際に飢え死にする可能性は低いのに、奇妙な不安を抱えているように見えます。
同時に、自分の望む人生を諦めなければならないことへの不安も抱えています。たとえば、私たちの祖父母世代は、「自分の望む人生」という概念すらなかったでしょう。食べて生きることで精いっぱいで、「個人」としての意識も薄かったからです。でも、「生存主義」に埋没せざるを得ない今の若い世代の大部分は、たとえ食べることができていても、「自分がほんとうにやりたいことをしていない」と感じて、とても苦しい状態に置かれています。日本も韓国も、若者たちは「望む人生をあきらめること」で不安を減らそうとしているように見えます。
でも、その矛盾は解決されていません。若者世代全体が、自分の所属している場所に所属感を感じられないというギャップに苦しんでいるように思います。どこかに所属していても、「ほんとうの居場所ではない」と感じている若者が多いのです。

