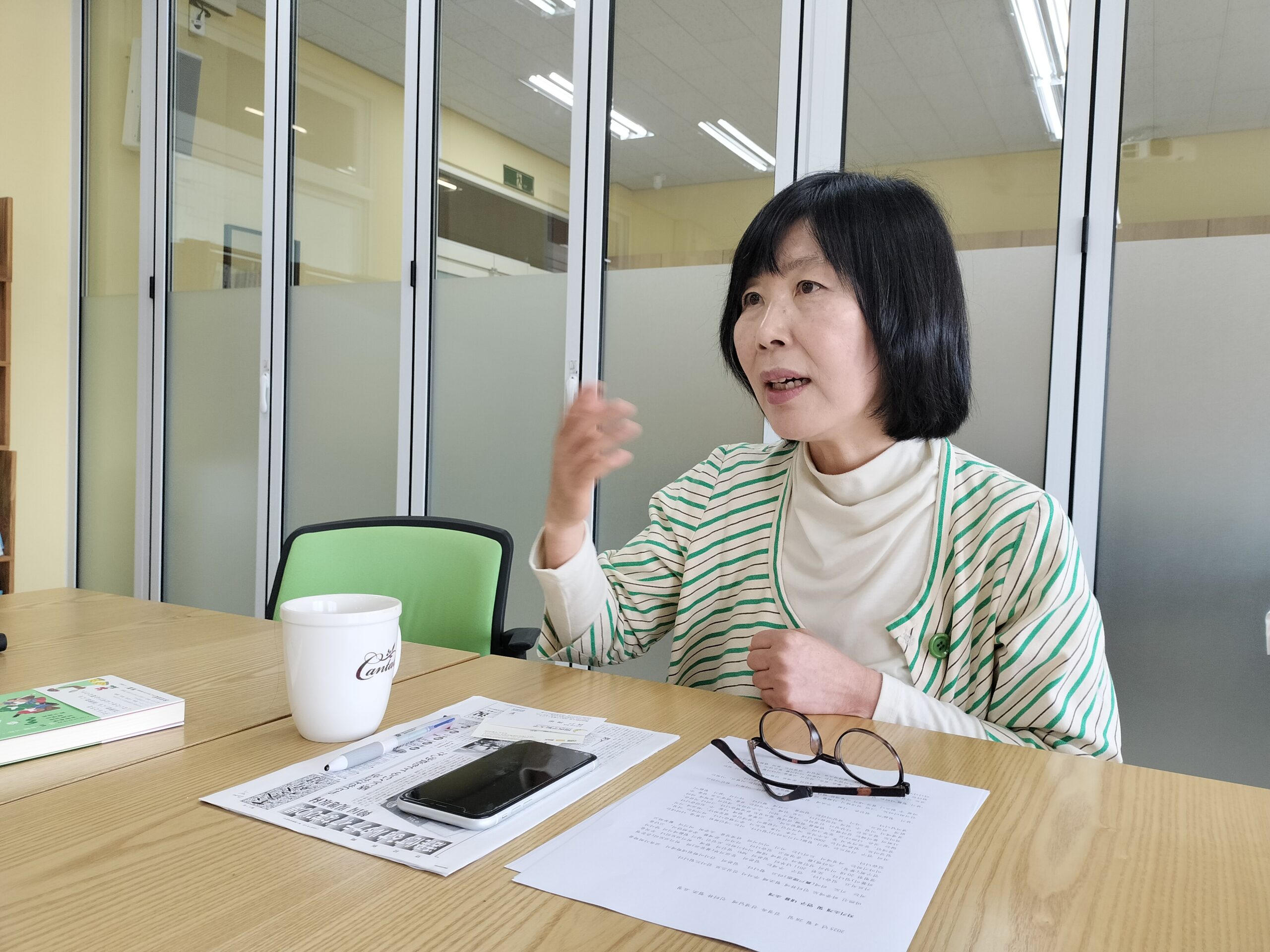絶望的な社会でも、生きていける「世界」を
――韓国の代案教育運動を振りかえって

◇ミンドゥルレとは
ミンドゥルレは日本語でタンポポの意味。1998年に出版社「ミンドゥルレ」設立。1999年に雑誌『ミンドゥルレ』創刊。その後、出版社に読者の子どもたちが集うようになり、2001年よりミンドゥルレ・サランパン(サランパンは居場所の意味)を開始、2006年より1年制のカリキュラムで学ぶ「空間ミンドゥルレ」に移行した。「空間ミンドゥルレ」の年齢層は原則13~18歳、在籍期間は1~2年、約20名が在籍。また、並行して2015年より、高校1年生が1年間を代案学校で学ぶ「オデッセイスクール」をソウル教育庁から受託し運営している。
https://www.mindle.org/
韓国では、2000年代以降、代案教育運動が拡がり、一定の社会的な位置づけを得てきている。その一方で、子ども若者にとって、社会状況はますます厳しくなっている。脱学校をテーマとした雑誌『ミンドゥルレ』を刊行しながら、「空間ミンドゥルレ」などの実践をしてきた金敬玉さんに、お話をうかがった。
日 時:2025年4月28日(ソウルにて)、6月13日(オンライン)
聞き手:貴戸理恵、山下耕平、花井紀子
写真撮影:山下耕平
貴戸:金さんが代案教育運動(オルタナティブ教育運動)にかかわるようになった経緯を教えてください。
金:代案教育という言葉は2000年代に入ってからのものですし、私は代案教育にかかわろうと思っていたわけではありませんでした。私は師範大学を出ているんですが、教員になりたかったわけでもなかったんです。自分が子どものころを思い返してみると、なかには良い先生もいましたが、卑怯だったり、差別をしたり、変な先生もたくさんいたので、そういう人にはなりたくなかった。けれども、私の時代には、女性は師範大学に行って教員になることが親たちの希望で、いわば親孝行のために仕方なく師範大学に入ったんです。
でも、大学に入ったら、授業はおもしろかった。とくに2年生のときには、授業でサマーヒルスクールやオルタナティブ教育の話があって、それはとても興味深かったんですね。ただ、それが韓国社会で可能だとはまったく思っていませんでした。それで、卒業後は中学校の教員を5年間していたんですが、その5年間はすごくつらかったです。倫理を教えていたものの、おもしろくないし、つらい。全斗煥の軍事独裁政権の時代でした。
そのころの一番の楽しみは、教員たちと自主的な勉強会をすることでした。80年代半ばごろは、全国各地に自主的な勉強会がいっぱいあったんです。1989年には、全国の自主勉強会が集まって話し合う機会がありました。教育はどうあるべきか、子どもたちの力になるためには私たちはどうするべきか、そういう考えを出し合って、意見を交わす。それが楽しみで、コツコツと地道な実践をしていました。たとえば遠足に行くとき、お母さんがお弁当をつくってくれない子どももいる。そこで、私たちがお弁当をつくって持っていったり、そんな実践をしながら教員をしていました。でも、どうしても子どもに役に立ってないような思いがあって、結局は5年で辞めたんですね。
その後、1990年に夫が東北大学に留学したので、いっしょに日本に行きました。仙台に住んで、市民グループで韓国語を教えたり、東北大の非常勤講師として韓国語の授業を受け持ったりしていました。その後、筑波に1年間行って、韓国に帰ったのが96年でした。それから2年ほどは、臨時で教員をしながら、いろいろ模索していました。
ちょうどそのころ、96年に韓国でガンディースクールが開校したんですね。その記事を雑誌で読んで、実際に訪問してみて、こういうことが韓国でもできるんだという感動がありました。
その後、99年に脱学校をテーマとした雑誌が創刊されるんですが、その雑誌をいっしょにつくる人を募集しているということで、私も編集にかかわらせてもらうようになりました。
貴戸:それが『ミンドゥルレ』ですね。出版社立ち上げの経緯を教えてください。
学校を超えて
金:代表の玄炳浩氏は、もともとは、ある有名な出版社で編集者をしていたんです。そこに、李韓という大学1年生の青年が、自分が高校3年生のときに書いた原稿を持ち込んできたんですね。すでに、いくつも出版社をまわっていて、どこの出版社でも「こういう内容では韓国では出版できません」と断られていたそうです。
玄氏は、その原稿を読んで、まさに韓国社会に必要な問題意識だと思って、その本を出版するために会社を辞めて、98年に新しく出版社を立ち上げたんです。そのときに刊行された本が『学校を超えて』という本です。

また、90年代半ばには、韓国の教育運動の変化を模索していた人々の勉強会があり、20名ほどが集まっていました。この勉強会は、その後の韓国の代案教育運動の流れをつくる大事なポイントで、ここで発想の転換が起きたんです。それまでの韓国の教育運動は、学校をどう変えるかという意識だったけれども、そこでどんなに一生懸命やっても、何も変わってない。それならば、これまでにない方法、これまでにない内容が必要ではないのか。そして、勉強会に集まった人のなかから、実際に代案学校をつくろうという人が出てきて、理念だけではなく、実際に目に見えるかたちになったんです。国が設置した学校ではなく、自分たちで教育実践をつくることができるんだという自信が出てきた。
そこで、それを社会に広くに知らせようと、99年1月に雑誌『ミンドゥルレ』を創刊しました。雑誌を出したら、この内容をいっしょに話し合いたい、もうちょっと知りたいという人が、たくさん出版社に来るようになりました(日本からも来ました)。そして、そのなかには子どももいたんです。
最初に来たのは、高校1年で学校に行かなくなった女の子でした。学校に行かず、あちこち出歩いていて、韓国で一番大きな本屋で『学校を超えて』を立ち読みしたということでした。「自分がなぜ学校に行かなくなったのか、自分にもわからなかった理由が書いてあった。この作者に会いたい」と、出版社を訪ねてきたんです。彼女はいっぱい話をしてくれました。そして、「自分以外にも、私のような子がたくさんいると思うので何かしたい」と言うので、雑誌に「いっしょに勉強しましょう」という彼女の声を載せたところ、次々に子どもたちが来るようになったんです。
でも、出版社の狭い部屋に十数名の子どもたちが来るから、編集の仕事ができない。私自身も、その子たちと話し合うのが仕事みたいになってきて、それなら別に部屋をつくりましょうということで、2001年に始めたのが「ミンドゥルレ・サランパン」でした(サランパンは居場所の意味)。
ですから、私は、自分から代案教育運動をやろうと思っていたわけではなくて、そうした流れのなかで、かかわるようになったんです。


居場所としてのサラパン
山下:サランパンは、どんな活動だったんでしょう?
金:ひとつのコミュニティ、居場所ですね。カリキュラムがあるわけではなくて、子どもたちが何かやりたいと言えば、それができるようにサポートしていました。そこには日本の東京シューレの影響もあったんですね。99年に東京シューレを訪問したとき、びっくりしたんですね。私はもともと教育に関心があって、教育というのは、子どもを変化させるためにある、その変化を支えることが大事で、子どもをケアするだけじゃなくて、成長を支えるべきだと思ってきました。子どもがみずから生きていこうという自信を持たせるためにも、学習が必要だという思いが常にあって、それをどのようにできるのかが、私の課題だったんです。でも、東京シューレは、子どもの居場所であればいいという。その考え方にはびっくりしましたし、影響を受けました。子どもを成長させなければいけないと思うのも一つの強迫観念じゃないか、もうちょっと、ゆっくりでもいいんじゃないか、いますぐ変化しなくてもいいんじゃないか。
貴戸:なるほど。東京シューレについては、あとでお話ししたい点もあるのですが、ほかに、影響を受けた教育思想家や実践家はいますか?
金:思想家では、デューイ、ペスタロッチ、イリイチ、それからフレイレですね。フレイレの影響が一番大きいです。
もともと私には、自分ひとりがしあわせになるのは申し訳ないという思いが強くあったように思います。中学校で教員をしているときも、学校に来ている子よりも、来られない子ばかりに目がいって、その子たちをどう支えられるのかという気持ちがありました。目の前にいる子どもを、何か少し手伝ってあげれば、「うん、大丈夫」と思えたりする。子どもが生きづらさを感じているのは、子どもに問題があるわけではなくて、社会やシステムの問題があるからで、社会を変えるということが、すごく大事だと思ってきました。なので、先に思想があって、それを実践してきたというよりは、私の出発点は目の前にいる子どもたち、まわりにいる人びとです。
それと、実践としては、日本で「きのくに子どもの村」を設立した堀真一郎さんの影響も大きかったですね。いろんな思想家や実践から学んでやってきました。まだまだ力不足ですが、先人から学んだことがあって、いま、私たちも実践できていると思います。