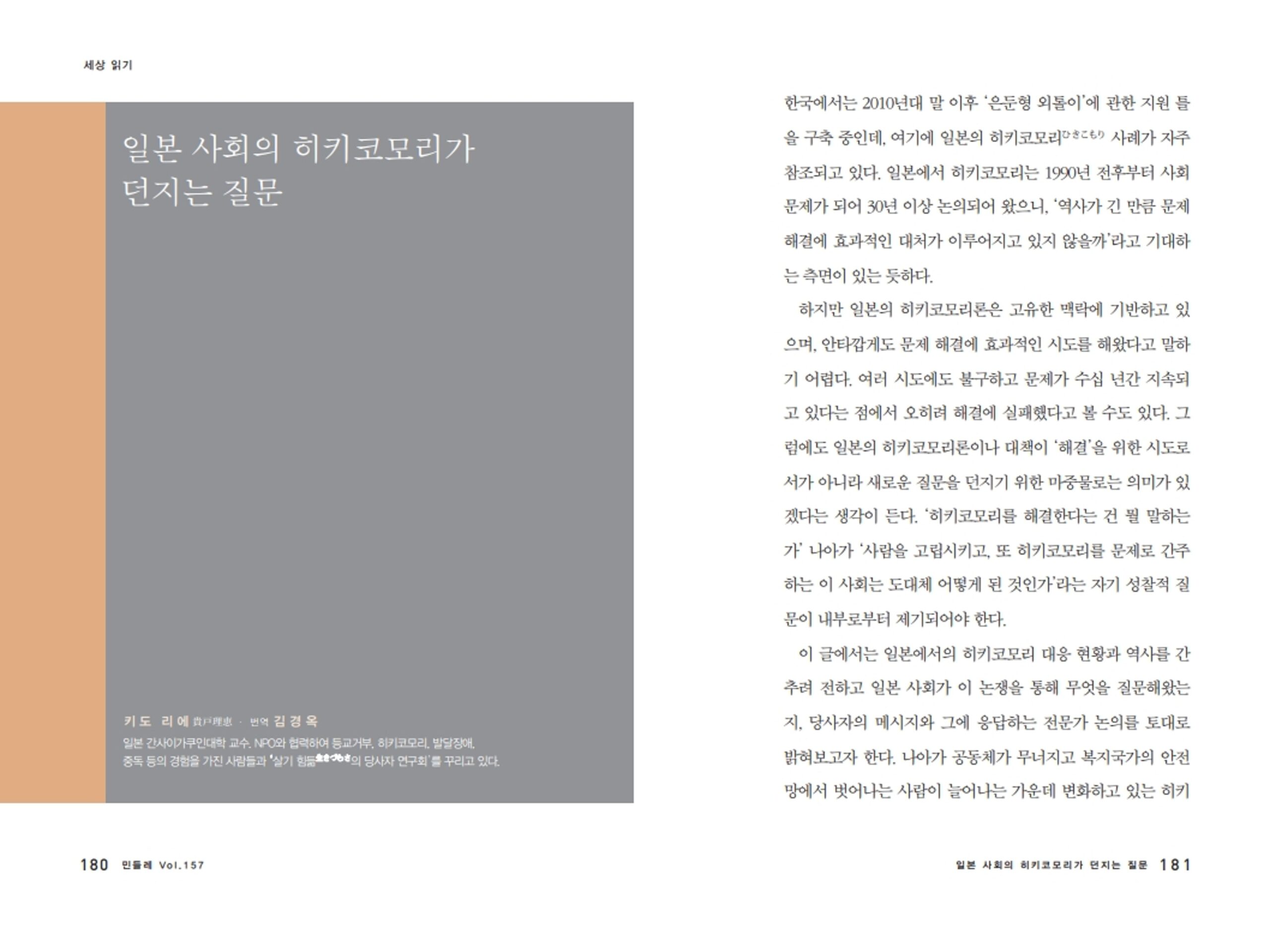貴戸理恵(関西学院大学)
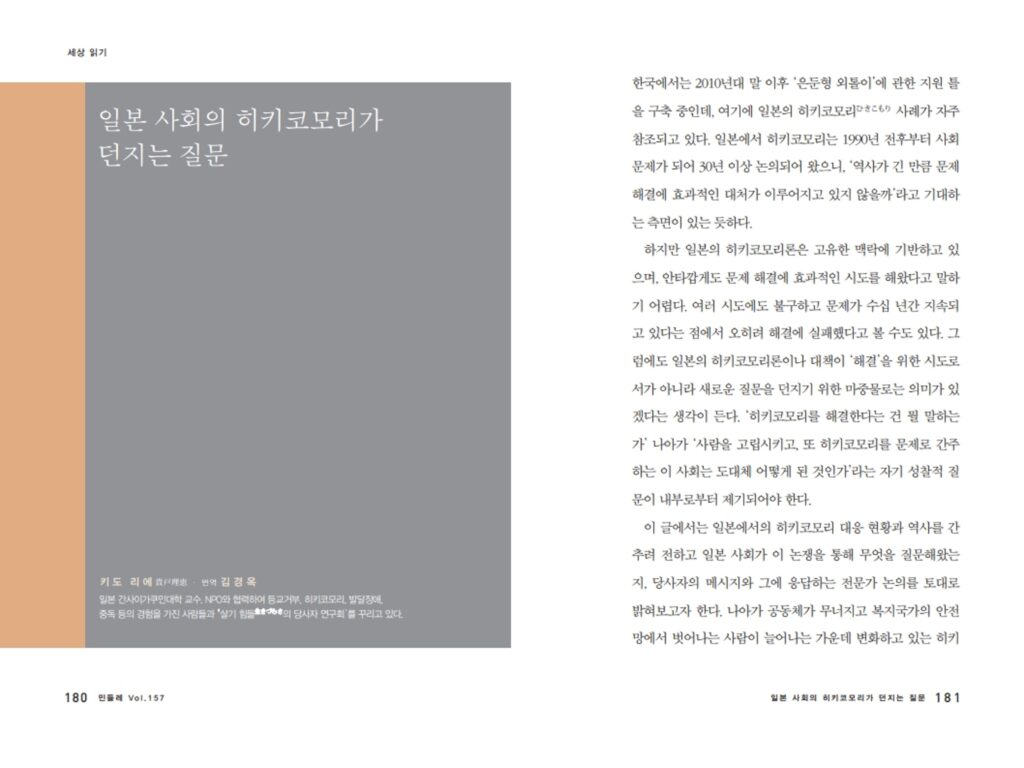
以下の記事は、韓国の出版社「ミンドゥルレ」が発行する雑誌「ミンドゥルレ157号(2025年 秋号)」に掲載された貴戸の原稿「히키코모리가 이 사회에 던지는 질문 일본의 히키코모리론을 중심으로」の元となった日本語原稿である。
2025年4月13日から8月5日まで、貴戸は韓国のソウルに滞在し、ひきこもり支援や若者支援についてインタビューをおこなった。4月25日から28日までは、18歳以上の居場所「なるにわ」と「生きづらさからの当事者研究会(づら研)」で貴戸とともに活動している山下耕平氏と、「なるにわ」やフリースクールを運営するNPO法人フォロに立ち上げから関わった花井紀子氏がソウルを訪れ、共同でインタビューを実施した。「ミンドゥルレ」編集主幹の金敬玉氏には、山下氏・花井氏の帰国後にも対面・オンライン混合でフォローアップインタビューの機会を設け、2回に分けてお話を聞いた(別記事参照)。
そうした縁から、貴戸に「日本のひきこもりをめぐる状況や議論について韓国読者に紹介してほしい」との原稿依頼を受け、雑誌「ミンドゥルレ」に短文を書くことになった。しかし、書いているうちに分量が増え、当初の依頼の4倍ほどになってしまった。編集部と相談し、私の主張の根幹部分と、韓国読者にとって意味があると考えられる情報を中心に、短く編みなおすことにした。以下では、この原稿を日本の読者にも届けるため、また元原稿を残すために、出版社の許可を得て、元原稿を全文掲載することにした。
翻訳と編集の労を取ってくださった「ミンドゥルレ」編集部と、原稿を読みコメントを下さった山下耕平氏、ソウルでの調査や滞在のアレンジに関わってくださったすべての人びとに心から感謝する。
1.はじめに
韓国では2010年代末以降、ひきこもり[은둔형 외톨이、隠遁型ひとりぼっち]に関する支援枠組の構築が進められており、日本のひきこもり論がしばしば参照されている。たとえば2019年に全国に先駆けてひきこもり支援条例(은둔형 외톨이 지원 조례)を制定した光州市の取り組みでは、支援施策や定義、実態調査などについて、日本の厚生労働省や内閣府、自治体の影響が見られる(光州市ウェブサイト)。日本ではひきこもりは1990年前後ごろから問題化し、30年以上にわたって議論され続けてきた。韓国社会のひきこもり支援において日本が参照される際、「歴史が長く、問題解決に有効な取り組みが進んでいるのでは」と期待されている面はあるだろう。
だが、日本のひきこもり論は固有の文脈に立脚しており、「問題解決」に有効な取り組みが「進んでいる」と一概に言うことはできない。それどころか、各種取り組みにもかかわらず問題が30年以上継続している点で、「解決」に失敗し続けていると見ることも可能だろう。日本のひきこもり論やひきこもり対策について他国が見るべきものがあるとすれば、「解決」のための取り組みでは必ずしもないと考える。むしろそれは、「病気のような合理的な理由がないにもかかわらず社会とつながらない」という現象に「ひきこもり」という固有の名称を与えた日本社会の内側から「ひきこもりの<解決>とはそもそも何か」ひいては「ひきこもりを問題と見なすこの社会とは何か」という自己言及的な問いを提出したことではなかっただろうか。
はじめに断っておくと、私の専門はひきこもりではなく、その近接領域である。私は社会学に立脚しながら、日本における不登校および「生きづらさ」という経験について、当事者の語りや対話的自助実践に注目して質的に研究してきた(貴戸 2004; 2022)。2011年からはNPOと協働で、不登校、ひきこもり、無業、発達障害、依存症などの経験を持つ18歳以上の人びととともに「生きづらさからの当事者研究会」という対話的自助の場を運営している。その過程でひきこもりを経験した人に多く出会ってきたし、ひきこもり論やひきこもりの当事者活動から多くを学んできた。
本稿では、まず韓国の読者のために、日本におけるひきこもりの定義や取り組みの現状と歴史を素描する。次いで、日本のひきこもり論が何を問うてきたのかを、主として当事者による発信やそれに応答する専門家の議論を通じて明らかにする。さらに、共同体が崩れ福祉国家のセイフティネットから漏れる人が増加するなかで、「ひきこもり」問題がより一般的な孤立支援の文脈に接続されていく経路について論じる。これらを通じて、韓国社会において은둔형 외톨이(隠遁型ひとりぼっち)に関わる人びとと、日本の「ひきこもり」に関わる人びととが、それぞれの問いを共有するための一助となることを目指す。
2.日本のひきこもり
2-1.定義
「ひきこもり」とは、精神科医の斎藤環によるもっともコンパクトな定義によれば、「6カ月以上、自宅にひきこもって社会参加をしない状態が持続しており、ほかの精神障害がその第一の要因とは考えにくいもの」(斎藤 2020:39)である。斎藤の定義はその後、厚生労働省や内閣府のひきこもり定義に影響を与えた。具体的には、2010年に厚生労働省が発表した「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」では、「社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、原則的には6カ月以上にわたっておおむね家庭にとどまり続けている状態(他者と交わらないかたちでの外出をしていてもよい)を指す現象概念である」とされている。また、2010年からおこなわれている内閣府による「若者の意識・生活調査」では、おおむね、外出の頻度と範囲がかぎられ、その状況が6カ月以上持続している人のうち、統合失調症や身体的な病気がきっかけではなく、妊娠、家事、育児、介護などをしておらず、仕事もしていない人をひきこもり状態と見なしてきた。
この定義のポイントは、「合理的な理由なく、個人が社会とつながらない状態」ということである。精神的にも身体的にも「病気」ではないのに、なぜか就学・就労せず、他者と関係をつくらない。そうしたある種の「不思議さ」が焦点化された定義なのだ。
これは、不登校の定義と共通性がある。文部科学省の「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によれば、「不登校」とは「何らかの心理的・情緒的・身体的あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況にある(ただし、「病気」や「経済的理由」によるものを除く)こと」である。これは年間30日以上欠席する「長期欠席」の理由別分類のひとつであり、他には「経済的理由」「病気」「その他」がある。つまり、病気や貧困など明確な理由がない長期欠席が「不登校」と呼ばれており、ひきこもりと同様に「合理的な理由なく、個人が社会とつながらない」現象を指す概念である。この点は不登校・ひきこもりが日本において「個人と社会とのつながり」を問い直す射程を持つことと関わっており、5項で立ち戻りたい。