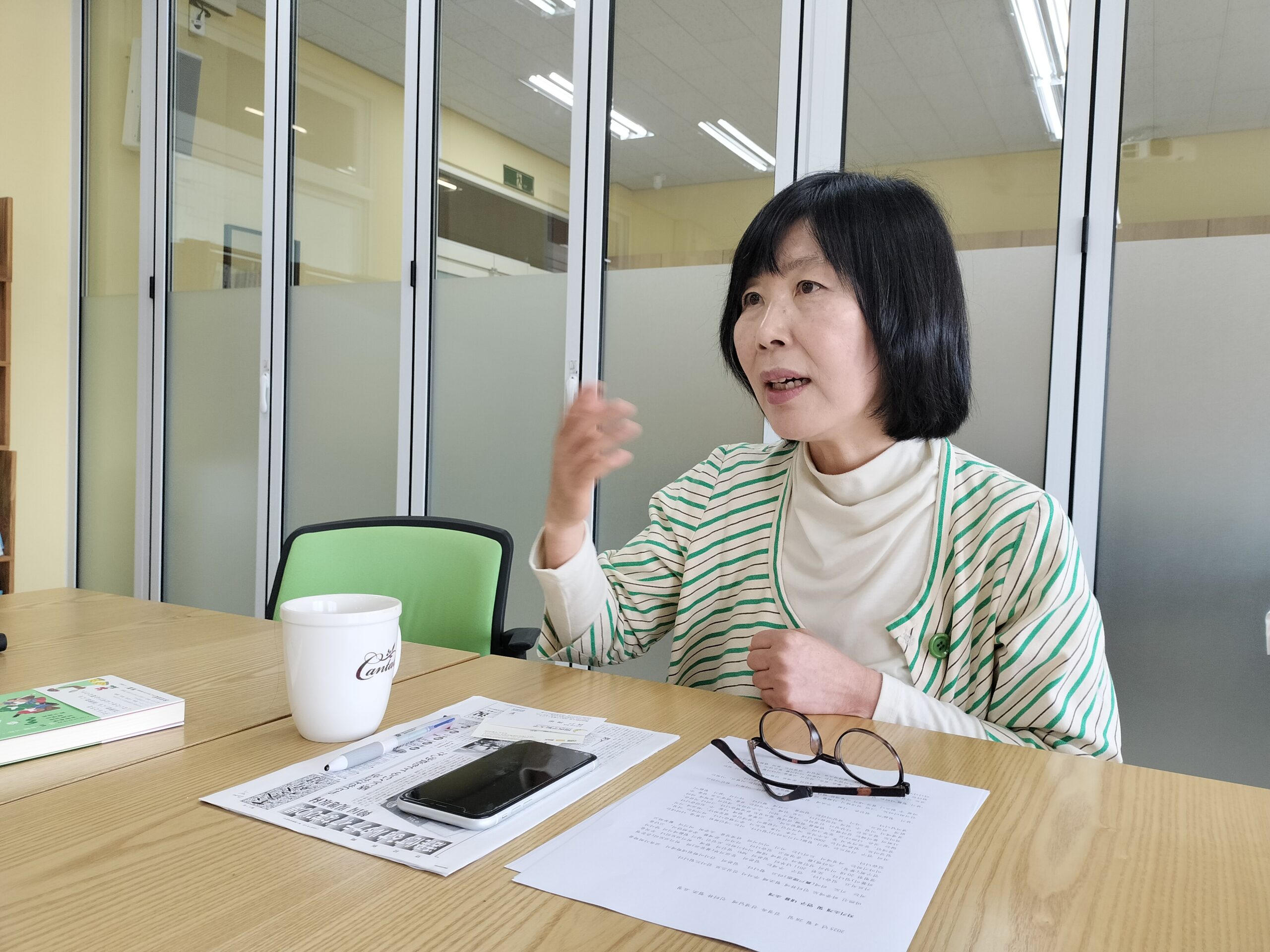足下の問題は
山下:私自身も、希望を捨てずに、身近なつながりを大事にしたいと思っています。それと同時に、夢物語を語るのではなく、起きている問題もちゃんと見ることが大事ということですよね。日本でも、東京シューレで25年ほど前にスタッフによる子どもへの性暴力事件が起きていたことがわかって、大きな衝撃が走りました。しかし、それは長年、隠蔽されていた。それは、フリースクールを社会に認めさせたいと思うあまりに、足下で起きている問題にちゃんと向き合えていなかったんだと思います。韓国でも、代案学校でそうした問題が起きているということはありますでしょうか?
金:そうですね。自分が一番正しいという権威的な教員の横暴があったり、ジェンダーへの感受性の差で葛藤が生じていたり、あちこちで問題は起きています。それをごまかして、何もないような顔をしていたところもありますし、反省を表明して「やり直します」と言っているところもあります。
一方で、はじっこにあっても一生懸命、内実を大事にしながら誠実にやっているところもいくつかあるので、そういう団体どうし、おたがいに尊重しながら、つながりながらやってきています。
なので、短期的に見れば、政策上の有利不利はありますが、長い目で見れば、こういう実践がほんとうに社会的に認められていくためには、直接的な支援よりも、ちゃんとした理念、見識を持ちながらやっていくことが必要だと思います。
社会というのは人々の目だと思うんですね。もちろん、すべての人を信頼できるわけではありませんが、ちゃんとした見識を持っていれば、それを理解して、つながりを持ちたいと思う人は、あちこちにいると私は信じています。
貴戸:原点となる価値に常に立ち戻ることが大事で、そこを揺らがせてまでほしいものは何なのか、ということですよね。研究者の世界もいっしょです。業績を上げるには、査読論文を書いて、国際学会で発表して、そのためにはこの話が適しているだろう、みたいな発想になりがちです。でも、それはあくまで手段であって、自分が一番伝えたいもの、やるべきことは何なのか、常に問われていると思いました。
金:いま、お話ししたのは、私が譲れないことを守るというよりは、この社会で必要であることは何かに目を向けるということです。いま切実に必要とされているものは何か、あるいは子どもが必要としていることは何か。そこは譲れないものがあると思っています。だから、行政と話し合うときも、自分が正しいと思うことを伝えるというよりも、これが必要だということを説得することに力を入れてきました。それが共感を得られれば一歩前進するし、共感してもらえなければ認められない。
なので、自分のアンテナを敏感にして、いま子どもたちに必要なものは何かを常にキャッチすることが大事だと思います。それをみんなに分かってもらえるように、一生懸命整理して、訴える。
当事者が問題意識を持っているのは、すごく大事だと思いますが、当事者性を超えて、その存在や考えを見ることが、より大事だと思います。不登校経験者としてのつらさを訴えるということだけではなくて、なぜ不登校がつらくなるのかを考えていけば視野が広がります。どう支援するかではなくて、この社会を変えていくために、たとえば行政の人間に、どういうふうに質問をして、どういうふうに説得すればわかってくれるか。
山下:それは、パウロ・フレイレが言っていたこととも重なりますね。
金:そうです。フレイレの言う教育というのは、すでに存在する世界に子どもを適応させることではなくて、子どもが、みずら新しい世界をつくっていく存在になるように応援することだと思います。
山下:しかし、お金の問題は悩ましいですね。私のかかわっているフリースクール・フォロでも、制度外にあるために、運営の問題は難しく、会費をもらわないとやっていけない。そうすると、ある程度の余裕のある家庭でないと、そもそも視野に入らない。フレイレの場合は、貧困層の子どもたちが、自分たちの置かれている状況を認識し、その社会を変えていくために識字教育が必要だということでしたよね。そのあたりは、どうお考えでしょう?
金:そこは、つらいところですね。オデッセイスクールをやろうと思ったのも、お金の問題がありました。オデッセイの場合は学費がゼロなんです。公立学校、いまは高校も無償化されているので。でも、やはり限界はありますね。
何を達成し、何を達成できなかったか
貴戸:最後に、韓国の代案教育運動の25年を振り返ってみて、それが達成したものと達成できなかったものは、何だったと思いますか?
金:いろんな社会変化のなかで、代案教育が一定程度、社会に位置づいたとは言えると思います。いろんな子どもたちがいて、いまの学校が苦しいものになっているということは、多くの人が認めるようになりました。いろんな多様な教育が必要だという認識にはなった。公教育のなかでも、多様な教育の場がつくられるようになりました。
でも、教育のまなざし、態度、文化が変わったかというと、そうではないと思います。私たちが目指しているような「学ぶ力」が、ほんとうに達成できているかと言えば、できていないと思います。持っている理念に対して、実践は足りていないと思います。
貴戸:山下さんも、花井さんも、30年以上前から日本のフリースクール運動にかかわってきて、何を達成して、何を達成しなかったと思いますか?
花井:私はフリースクールを引いてから10年近くになるので、まずは、自分を振りかえる機会となったことがよかったです。30年前と比べたら情報量は圧倒的に増えて、情報の質は別として、行き先やつながる場が増えたのはよいことかもしれないと思いますが、それでしあわせな人が増えたかというと、そうではない気がします。それがなぜなのかは、みんなが考えていかないといけないなと思います。
それと、自分自身、子どもたちとかかわることを通して、いろんなことを考えてきたなと、あらためて思いました。それが、たとえば自分の親の介護のことにつながっていたり、これから自分が高齢になっていくときに、どうやって生きていくかを考えることにつながっていたり、人生全体のことにかかわっている。それは、社会の問題ということでもあると思いますが、そういう、いろんなことをつなげて考える種を、たくさんもらってきたなと思います。
山下:日本でも、教育に多様性が必要というメッセージは、社会に受けいれられるようになったと思います。でも、その一方で、人を能力で選別していくという流れは、むしろ強まっている。受験勉強だけで人を選別するのではなく、選別のまなざしも多様化して、多様に人が選別されるようになってきている。それと、社会全体が市場化してしまったなかで、多様化された教育には、教育産業が入り込んできていて、ICT化とともに、どんどん拡大しています。そうしたなか、フリースクールの運動は、かつては社会運動だったものが、多様な教育商品のひとつになりつつあるように思います。
それと、私の関心としては、教育のあり方よりも、不登校を経験した人やフリースクールで育った人が、その後どうやって生きていけるのかに焦点が移っているところがあります。なので、いまもフリースクールにかかわってはいるものの、子どもと直接かかわってはいなくて、18歳以上の人たちの集まりを開いたり、当事者研究をしていたりします。
ますます厳しくなる社会状況のなかで、教育だけがオルタナティブであればいい、ということではすまない。でも、そういうことを関係者とちゃんと話し合えているかといえば、だんだん難しくなって、はじっこに来ちゃったみたいな感じがあります。でも、金さんがおっしゃったように、信頼できる人、つながれる人はいますし、社会状況を直視しながらも絶望するのではなく、地道にやっていくことが大事だと、あらためて思いました。こうやって、国境を越えてもつながれますしね。その意味でも大事なインタビューになりました。ありがとうございました。
貴戸:ありがとうございました。