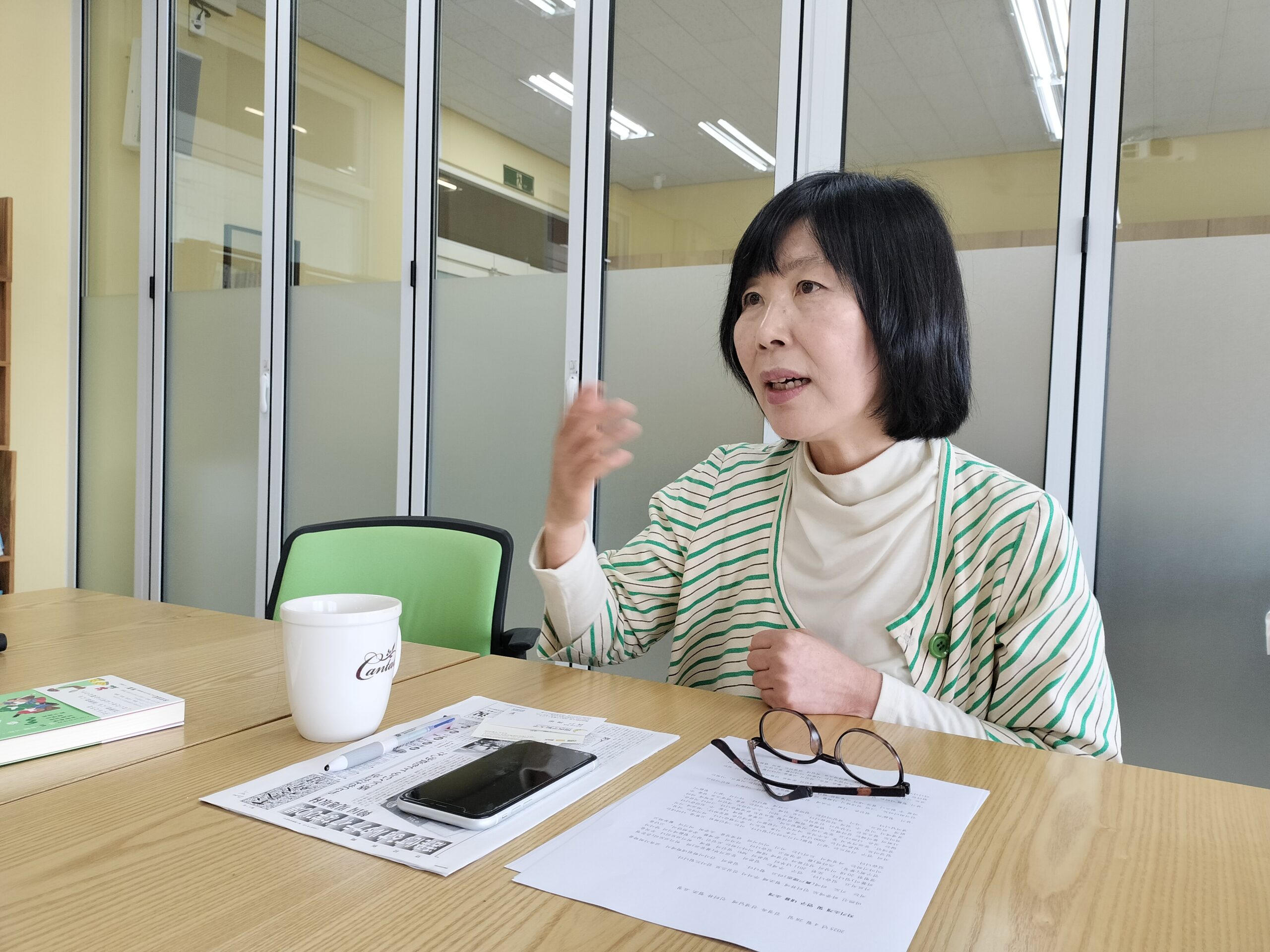希望的な語りの問題
貴戸:日本のフリースクール運動のなかでは、学校に行かなくても大丈夫、フリースクールという選択肢があるし、自分のやりたいことを見つけていけば、社会でやっていけるという希望的な物語がたくさん語られ、それが受けいれられていた時代がありました。私は、それ自体はとても重要なことだと思いましたが、私が社会に出た時代は2000年代で、就職氷河期でした。そのなかで疑問が湧いてきました。不登校でも社会に出ていける、仕事をして経済的に自立していけるという言い方は、それだけでいいのだろうか。学校に行っていても就職できない人がたくさんいますし、統計上は、不登校経験者の場合、正規雇用率も、高校を卒業する割合も、大学進学率も低い。学校に行かなかったあと、社会とつながることができず、ひきこもっていく人や無業のままでいて、うつ病を患ったり、精神的なしんどさを抱えて、人や社会を信頼できずに孤立していく人もいる。だからやっぱり不登校はだめだ、というのではなくて、そういう「その後」のしんどさも含めて不登校経験を受容する言葉を探りたい、と思ったのが私のスタートでした。
金:それは大事な問題意識だと思います。韓国では「不登校」という言葉は使っていませんが、「学校の中の子ども」「学校の外の子ども」と言っています。代案学校に通っていても、社会的には「学校の外」であって、そのことはやっぱりリスクなんですね、韓国社会で就職するには学歴があって、人脈があって、そのうえに自分の実力が必要とされる。なかでも、一番重視されるのが学歴です。代案学校を出た人には、学ぶ力や実力があっても、学歴と人脈は足りない。そこで、いろいろ壁にぶつかってしまう。
でも、学歴も人脈もあって、いい仕事に就けている人というのは、人数から見れば少数です。むしろ私たちが多数派なんです。そこで、学歴や人脈でつながるのではなくて、その人自身をみて、つながることはできる。
ただ、貴戸さんの問題意識はよくわかります。韓国の代案教育は、この20年間で評価されて拡がってきましたが、穴もいっぱいあったんですね。希望的な物語はあっても、その物語を成り立たせるための実力は足りなかった。だから、代案教育で育った子どもたちがみんな幸せかと思うと、そうではないと私も思います。
ですから、私もその流れのなかにいたひとりとして、反省があります。その反省のもとで、常々思うのは、学歴や人脈ではない、その人のもつ「力」は大事だということです。分別する力、コミュニケーションする力、勇気。それを育てていくこと。そのプロセスを持たずに、ただ希望的なメッセージばかりを子どもたちに浴びせるのでは、私はダメだと思います。
山下:学歴や付加価値をつけることに尽力するよりも、自分の内側にある力を育てて、信頼できる人とつながって生きていこうということですよね。どんなに悲惨な社会状況のなかにあっても、希望や人への信頼を見失わずに生きていこうという思いは、とてもよくわかります。私も祈りを込めてそう願っていますが、一方で、代案教育を社会に認めてもらうために、実際以上に成功の物語を語ってしまってきたという問題はないでしょうか? 日本では、そういう面があったと思います。
金:そうですね。いろんな穴があったと思います。代案教育の言葉が、能力主義やエリート教育に流用されたり、教育を歪曲させる役割をはたしたりもしました。そういう話は、雑誌『ミンドゥルレ』でも、長年取り上げてきました。でも、見て見ぬふりをする人も多く、とくに国と折衝する際には、フタをしてきたところがあったと思います。それは恥ずかしいことですね。
ですから、オデッセイスクールを始めるときは、ソウル市には私たちの見職をきちんと示して、それをベースに話し合ってきました。ただ、オデッセイスクールは10年目になりますが、今後どうなるかはわかりません。韓国ではめずらしい仕組みで、それゆえに攻撃も受けやすいんですね。それと、韓国国内でもっと拡がっていけばいいんですが、なかなか難しいというのが現状です。この仕組みを国内に定着させていくには、私たちの力が不足していると思っています。

貴戸:民主主義というのは、結果ではなくて、みんなが参加して決めていくというプロセスにあると思います。日本でもコロナ禍を経て、不登校の数が増えていて、行政が不登校支援の枠組みをつくろうとしています。そこで、プロポーザル方式で各団体に競争させて、もっとも成果が見込める事業にお金を出すというかたちになると、支援者の側は、「自分たちはこんなにすばらしいことをやっています」と美化して語らなければならなくなってしまう。さらには、実績といっても、利用者数だとか学校復帰率だとか、表面的な成果を語ることになってしまう。そうすると、「成果」になりそうなものが支援の前面に出やすくなり、子どもや親にとってどうかが後回しになってしまう。そういう逆説があると思っています。
金:私たちは世の中を握っているわけではなくて、ほんの一部なんですよね。同じ考えを持っている仲間だと思っていた人でも、実際の考えはそれぞれで、そこで失望したり、がっかりすることも多いです。だからこそ、自分自身の誇りを失わずにいることが、すごく大事だと思っています。ミンドゥルレでいっしょに働いているスタッフたちの誇りも大事です。みんな、人間として自分の存在を大事にして、自分自身がどう生きていくのかに悩み抜いて、ミンドゥルレに来ていると思っているので、それをおたがいに大事にしながら、話し合っています。
はじっこに
金:ミンドゥルレは、代案教育の運動をしている人のなかでも、いわば「はじっこ」なんですね。一時期は中心的に動こうとしていたときもあったんですが、できなかったんですね。
貴戸:それは、具体的にはどのような経緯だったんでしょう?
金:もともとは運動としてやってきたことが、財政支援の段階となると、難しい局面になるんですね。オデッセイスクール検討の際も、制度設計を考える段階になると、お金の話が中心になってしまった。そういうとき、私はお金のことは重視しないスタンスをとって、そこであきらめざるを得ないこともありました。何をあきらめるかというとき、お金や権力をあきらめる、理念はあきらめない。そのようにしていたら、運動のはじっこに来てしまいました(笑)。
山下:金さんとは、経緯も立場も異なりますが、私も、自分の問題意識を大事にしていたら、運動のはじっこに来てしまった感じはあります(笑)。そこで悲観するのではなくて、お金よりも、自分が誇りに思えること、信じられる部分を大事にしてやってこられたというのは、すごく大事なことだと思いました。
金:だからこそ、信頼されている面もあると思います。とくに、地域からの信頼はあります。だから、子どもたちが地域で何かを学ぼうと思えば歓迎してくれるし、そういうつながりは大事です。