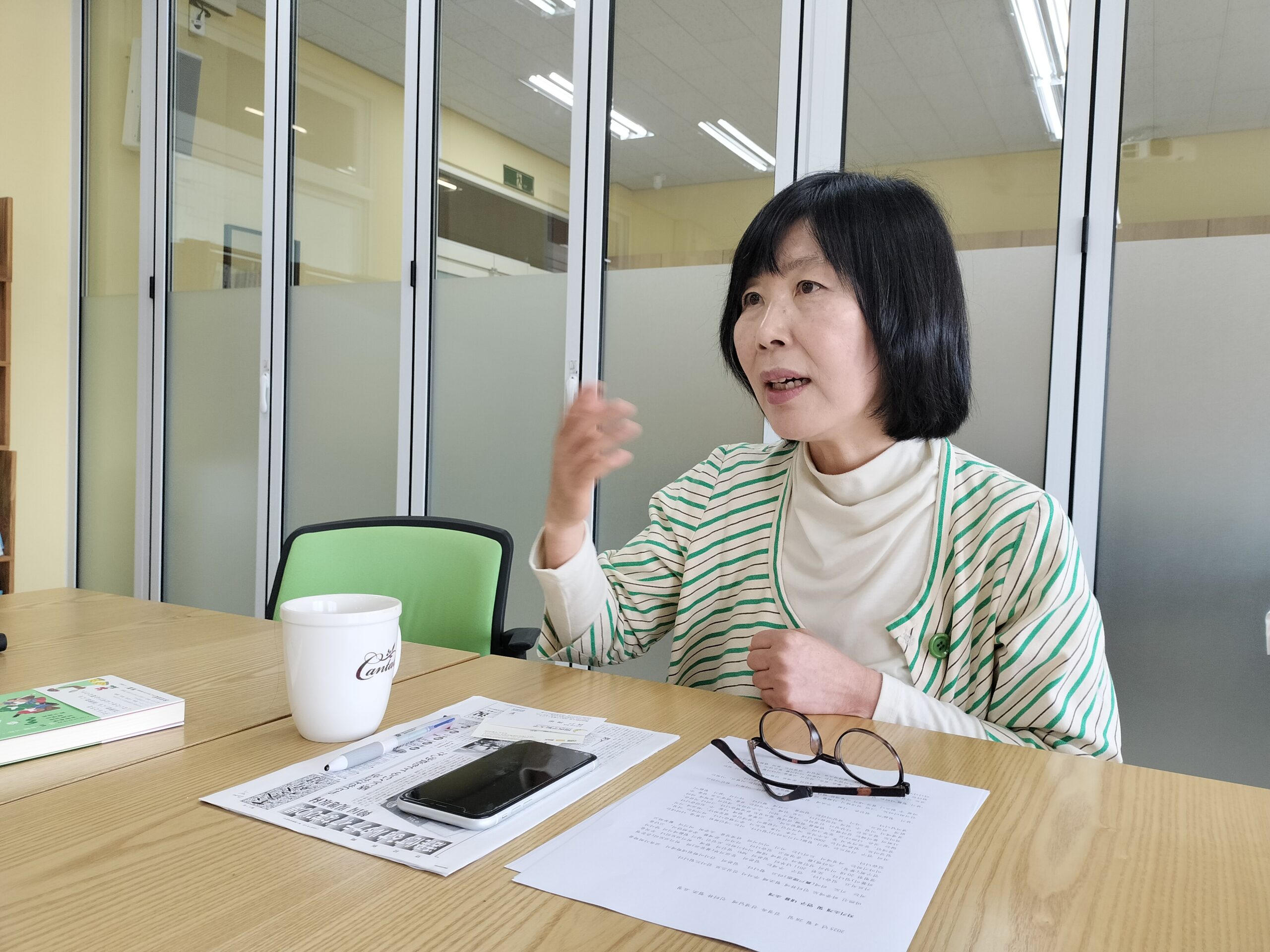スタッフ間のコミュニケーションは?
花井:いっしょにつくっていくという感覚が、スタッフどうしでも難しくなっているということはありますか?
金:さいわい、ミンドゥルレでは話し合いながらやっていけていると思います。ミンドゥルレには、まず雑誌があって、その雑誌を長く読んでいるなかで問題意識を持って、共感してくれる人たちがいます。その人たちがミンドゥルレを訪ねてきて、自分にできるかかわりをしてもらっているうちに、スタッフになる人が出てくるんです。韓国語で「어슬렁 거리는 사람」(ぶらぶらしている人)と言いますが、のんびりミンドゥルレに通うなかで、時間をかけて信頼関係をつくってから、スタッフになってもらっています。
私たちは、規模も小さいので、おたがいに助け合って、話し合いながらやっていくことができているんだと思います。ただ、これからどうなるかは、わからないですね。
山下:世代的な差は感じますか? 初期の代案教育運動の担い手は、民主化運動世代の人が中心ですよね。日本でも、初期のフリースクール運動は、60~70年代の社会運動を担った人たちがかかわっていました。そこでは、たんに教育だけの問題を考えるのではなくて、いろんな社会問題を考える問題意識があって、教育運動にもかかわっていたんですよね。でも、いまは社会運動というよりは、この社会で個人がどうやって生きていくかという、個人化した教育サービスの問題になってきているように思います。韓国では、どうでしょう?
金:ミンドゥルレは規模が小さいので、世代差の問題はあまりないと思います。もちろん、話し合いがうまくいかなかったり、葛藤が生じることもありますが、それは世代の問題ではないと思います。一番若い人が32歳の女性ですが、ガンディースクールの出身なので、ガンディースクールで学んだこと、文化、指向性があるんですね。そのうえで、ミンドゥルレでも講師としてかかわり始めて、だんだんなじんでもらってから、スタッフになりました。
でも、子どもと接するなかでは、もめごとはあります。そういうときは、いっぱい話をします。なので、いつも会議です(笑)。何かと言えば話し合っています。一方で、口に出さない不満があるときには、私は気づいても知らん顔をします。言葉にして話し合うことが大事ですから。それがめどうくさいときもありますが、ここでは、とにかく話し合います。
山下:スタッフのなかで、ほかにも代案学校の出身者はいますか?
金:代案学校の出身者は、彼女ひとりですが、ほかの代案学校でスタッフをやっていた人は3人います。新卒でスタッフになる人はいないですね。
山下:20名という規模は、あえて保っているということですかね。
金:そうですね。私は、このスタイルでよかったと思っています。でも、ほかのスタッフみんながそう思っているかはわかりません。もうちょっと規模が大きく運営できたほうがよいと思っている人もいると思います。
山下:経営重視になってしまうと、そこで失われるものはあるでしょうね。スタッフの継続年数は、どれぐらいでしょう?
金:一番長い人は13年目ですね。入れ替わりは多くはないです。

卒業後の困難は
山下:日本では、フリースクールで過ごしているあいだはオルタナティブな価値観を共有できていても、その後、社会に出ると、社会はより競争的で大変な状況になっていて、そのギャップに苦しむことはあると思うんですね。そういうなかで、「フリースクールのスタッフはいいよね、大人になってもオルタナティブな価値観を大事にして働いていられる」という声を聴くことが、ままありました。それは、フリースクール以外で、そういう価値観で働ける場は少なくて苦しいということだと思います。そのあたりは、ミンドゥルレの卒業生の人たちの場合はいかがでしょう。
金:それは、たしかにあると思います。そこで苦しんだり悩んだりしている人は、けっこういると思いますが、同じ時期に通っていた人どうしで、そういう話をしながら、おたがいに支え合っています。
私自身のことを言えば、ミンドゥルレを選んだのは、「職場」を選んだというよりも、「世界」を選んだのだと思います。社会といっても、そのなかにはいろんな「世界」があって、自分と合う「世界」と接触することが一番です。それが進路だと思うんですね。どんなところにいても、人間関係はたいへんですが、いろんな人がいるから、なかには自分と合う人もいる。そういう人と出会えることが、この複雑な世の中を生きていくうえで大事かなと思います。なので、ミンドゥルレでも、そういう練習をしてほしいと思っています。社会の全部を否定するんじゃなくて、自分を受けいれてくれる人や世界と出会っていく。この社会は自分と合わないというように、全面的に悲観するような考えは持ってほしくないと思います。
山下:そうですね。でも、若い人が悲観せざるを得ないような社会状況もありますね。
金:もちろん、社会の状況は厳しいです。韓国は日本よりも厳しいかもしれません。絶望的で、問題はいっぱいあるんだけど、一方では、私たちのように、一生懸命、自分の世界をつくりながら、つながる人を探している取り組みもある。そういうふうに、一生懸命やっている人は、どこかにはいる。だから、日々、子どもと接しながら、この世の中のよいところも知らせていくことも私たちの役目だと思っています。
でも、子どもたちが卒業するときは、毎年、別れるのが寂しいのではなくて、こういう社会に出て行くのはかわいそうだと思って、涙が出ます。だから、いつも祈っています。自分が生きていける世界を見つけてほしいと思って。
貴戸:おっしゃることは、よくわかります。私自身を考えても、自分が自分のままで接続できる社会ってどこにあるんだろうと考えながら生きてきたように思います。若いころは、自分を殺して社会になじむか、自分のままでいて社会に接続できないかと、二極化して捉えていたところがありましたが、そんなことはないはずだと思って、自分のままで接続できる社会を探してきた。でも、私の場合は、そういう世界をたまたま見つけられたからよかったけれども、そうできない人もいますよね。ミンドゥルレを出たあと、家にひきこもっていたり、無業のままでいる人はいますか?
金:います。たとえば、男性は韓国では軍隊に徴兵されますが、軍隊では、自分のままを認められることはまったくないですね。そこで、すごくつらい目に遭って、苦しくなっている人もいます。あるいはセクシュアル・マイノリティで、それゆえに自分らしく生きられる世界と接触することが難しく、ひきこもっている人もいます。比率で言えば、大勢ではありませんが、苦しんでいる人はいます。それと、卒業後も連絡をくれる人はようすもわかりますが、連絡のない人もかなりいるので、私もわからないところはあります。
ただ、その人の人生を、すべて背負えるわけではないですからね。私たちとしては、いま目の前にいる子どもたちとかかわって、世の中に出ていく力を育てていくことを一生懸命やっている。送り出すときは、涙を流しながら祈る。それしかできないと思っています。だから、韓国の社会がよくなってほしいと切実に思います。
山下:どんな絶望的な状況があっても、できることに限りはあっても、地道に、できることをやっていくしかないですよね。
金:私自身が悲観的にならないように気をつけています。悲観的に思えば、すべて意味がないと思えてしまいますから。私たち以外にも、一生懸命、世の中のために活動している人はあちこちにいます。社会には昔から問題はいっぱいあるけど、でも、少しずつ民主的になっていて、いろんな少数者が認められたり、そういう世界になっている。そういう人とのつながりを持って生きていこうと言いたいです。国を越えて、日本にもそういう人がいるし、アフリカにもいるし、そういう人々のつながりが私は大事だと思っています。インターネットもありますから、家にこもっていても世界に接続できる。