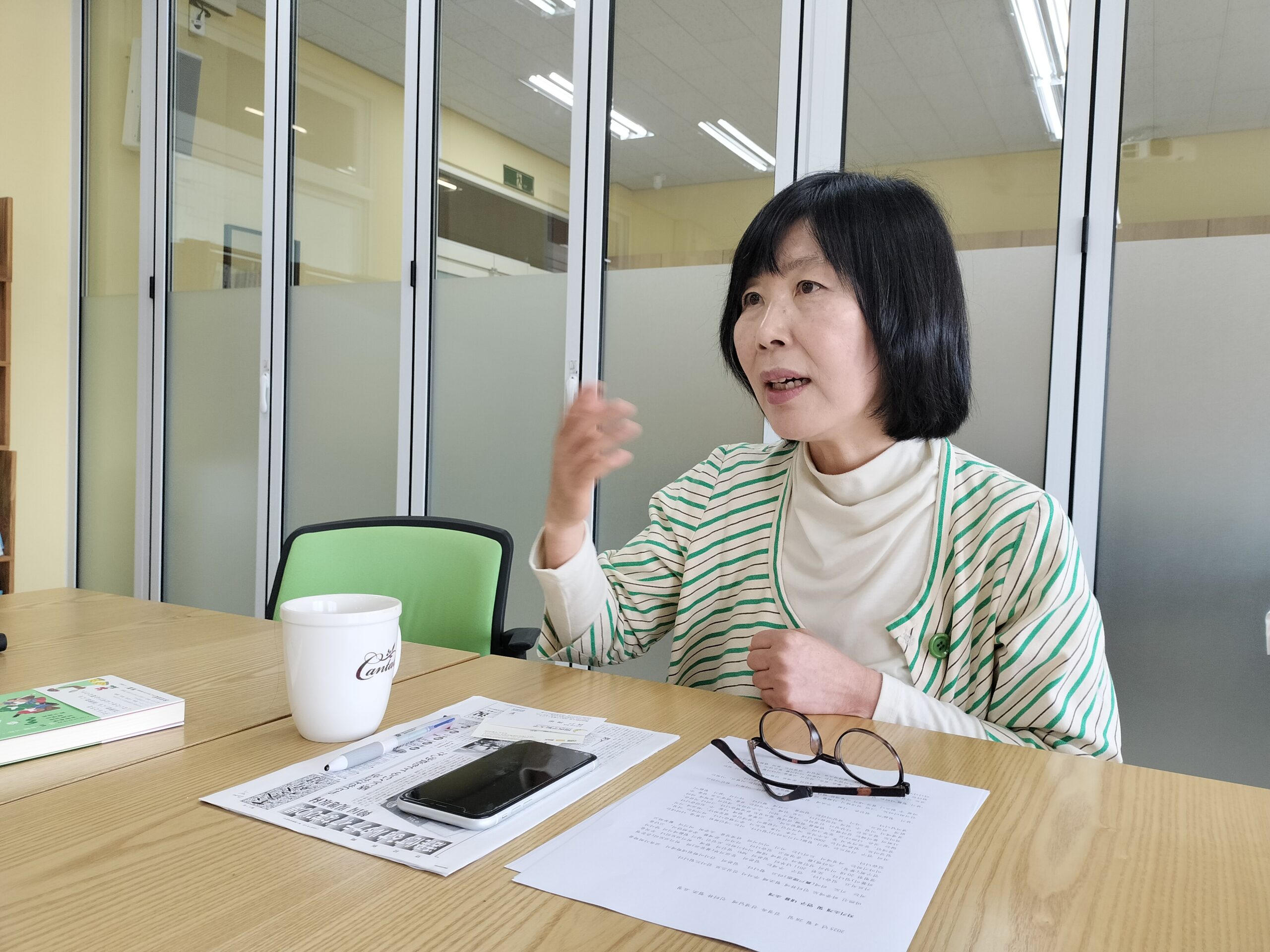金:2014年に事態が大きく動きました。その年の4月に起きたセウォル号事件の影響があったんです。事故発生後、早めに脱出していれば助かるはずだったのに、子どもたちは上からの指示に従って、船室から脱出しなかった。そのために多くの命が失われました。そこで、多くの教育関係者が反省したんですね。韓国の学校教育はこのままでよいのか、自分で物事を考えるのではなくて、上からの指示に従っていることでよいのかと。これからは、自分の頭で考えてほしい。自分の人生はみずから考えながら歩んでいってほしい。そういう意見が社会的に共有されるようになって、代案教育が注目を集めたんです。
それと、私たちが制度外の実践に限界を感じていたこととが重なって、学校の中でも代案教育の実践を採りいれるべきだという流れに、私たちも応じていったんですね。そこで、学校制度の内と外の人たちが協力して、オデッセイスクールが始まりました。
山下:空間ミンドゥルレは、いまでも制度外で活動しているんでしょうか?
金:2006年の法改正では、学校法人しか認められませんでしたから、空間ミンドゥルレは学校制度とは程遠かったので認められることにはなりませんでした。ですが、2022年に代案教育機関支援法が施行されたんです。それまで学校として認められていないところでも、子どもの勉強や教育を支えているのであれば、その機関をある程度は認めて支援するという法律です。この法律によって、空間ミンドゥルレもソウル教育庁に登録して、人件費の一部(25万円×4名分)やお昼代が支援されるようになりました。教育内容にはまったく干渉しないので、私たちも自由にやれています。
山下:人件費とお昼代以外の補助金は出ているんですか?
金:家賃は出てないんですが、運営費が少し出ます。でも、政権交代の影響もあって、以前よりだいぶ減りました。運営費のために、ミンドゥルレでは学費(月額55万ウォン/約5万5000円)をもらっています。
スタッフ体制は
貴戸:スタッフは何人ですか?
金:常勤スタッフが7名で、そのうち2名はオデッセイに派遣しています。ほかに、非常勤スタッフ(講師など)が13名います。
貴戸:スタッフに資格は要りますか?
金:ミンドゥルレでは、経験があれば、免許はなくても大丈夫です。オデッセイには3人のスタッフがいますが、そのうち2名はミンドゥルレからの派遣で、1名が公立学校からの派遣です。当然ですが、彼らは教員免許を持ってます。
貴戸:行政の枠組みでやっているオデッセイでも、教員免許のない人がスタッフとしてかかわれるんですね。
金:オデッセイスクールは委託システムなので、ミンドゥルレがすべての責任を持ちます。そこで、免許があってもなくてもかまわないという仕組みをつくったんです。一方で、高校1年としての記録は必要なので、その書類は公立学校から派遣されたスタッフが担っています。
韓国では、ソウル以外でも2カ所、オデッセイのような取り組みをしている地域がありますが、どちらも、スタッフには教員免許が必要です。ソウルのように、代案教育のスタッフが教員に入るのは、ほかのところでは難しいようです。
山下:オデッセイスクールは、高校1年の学習課程として認められるということですが、空間ミンドゥルレの場合にも、公的な学習課程として認められるんでしょうか?
金:それは、ないんです。なので、進学したいときには、検定試験を受けて卒業資格を取っています。
山下:韓国では、日本みたいに在籍したまま不登校になることはなくて、義務教育でも欠席日数が多いと除籍になるけれども、検定試験を受けて合格すれば卒業になるということですよね。
金:そうです。小学校、中学校、高校とも、試験は1年に2回あります(4月と8月)。学校を辞めてから6カ月を過ぎると、この試験を受ける資格を持ちます。試験の内容はそんなに難しいものではありません。最近は、検定試験を受けて大学に行く人が増えてます。
というのは、韓国では高校で5段階のレベルに分けられて、そのレベルに応じて受験できる大学が分けられるんです。1番上のレベルに入るためには、競争がすごく激しい。でも、高卒の検定試験ですべて100点をとれば、1番上のレベルに認定される。そうやって検定試験を利用して大学受験する人も増えてます。

消費社会のなかで
山下:ミンドゥルレの人たちも、進路は大学進学が多いですか?
金:そうですね、最近はとくに大学に行く人が多いです。日本でも同じかもしれませんが、年齢が20歳を過ぎても自分のことを大人だとは思いにくくなっている印象があります。なので、高卒で社会に出る決心ができなくて、まだ準備したいという気持ちもあるのかなと思います。
山下:以前はちがいましたか?
金:自分で何かビジネスを始めたり、田舎に行ってみたり、いろんな挑戦をする人もけっこういました。ここ5~6年では、そういう子はほとんどいないですね。
山下:なぜ、そういう変化が起きたと思われますか?
金:それは教育問題だけじゃなくて、社会全体の構造の問題もあると思いますが、親たちの影響も大きいと思います。
山下:日本もすっかり消費社会になっているので、与えられるものを消費することが生活になっていて、自分たちでイチから何かをつくりだすみたいな感覚は薄れているように思います。親世代も生まれたときから消費社会のなかでで育ってきているので、そういう影響もあるのかもしれないですね。
金:それも大きいと思います。親たちも、子どもにお金をかけたり、一生懸命ケアしているんだと思いますが、方向性がまちがっていると思います。
山下:韓国の代案教育には、都市型と農村型があって、近年は都市型が増えているとうかがいましたが、かつて農村型が多かったのは、イリイチの影響はありましたでしょうか? イリイチは近代化批判として、土着的な生活に根づくことが大事という視点から、脱学校と言ってましたよね。
金:そうですね。ガンディースクールもそうですが、エコロジー思想がありますね。あとは、代案学校が農村にあったのは、学校をつくりたかったからだと思います。一定の広さの土地があって、教室や運動場が必要だという、想像力の限界があったんだと思います。でも、代案教育の場合は、運動場がなくても、規模が大きくなくてもいいという想像力が生まれてきて、都会で始める人が出てきた。ニーズのある子が多いのは都市部ですし、だんだん、ソウルや釜山など都市部に、小さな学校ができてきました。
主体的な学びが難しくなっている?
山下:ミンドゥルレの「学ぶことを学ぶ」「ともに学ぶ」という2つの柱は、自分たちが主体的に学んでいくということだと思いますが、いまの時代状況のなかで、それが難しくなっていると感じることはありますか?
金:たしかに、ミンドゥルレを始めたころは、子どもたちがいろいろ挑戦していたのが、いまは難しくなっていて、私たちの対応も変わりました。それと、みずから学びをつくりだしていくところまでいくには、ミンドゥルレだけでは足りないと思っています。その意味で大学の進学を勧めることも、よくあります。それは一流大学を目指すということではなくて、いい先生のいる大学もあるんですよね。そこで、もっと深い勉強してから社会に出るのがよいかなと思います。
山下さんは、日本の状況をどう思っていますか?
山下:やっぱり、すごく難しくなっているように感じています。私がフリースクールにかかわり始めたのは90年代初頭ですが、それからしばらくは、子どもたちがミーティングで自治的に話し合って、活動をつくっていくということが、かなり活発だったと思います。でも、だんだんそういうことが難しくなってきた。それがなぜなのかは、あまり短絡的に考えてはよくないと思いますが、ひとつには、先ほど申し上げたように、消費社会が浸透して、親も消費者感覚で子どもをフリースクールにあずけるし、子どものほうも、時間や興味を消費サービスに奪われているところがあるのかなと思います。子どもの主体性を大事にするといっても、放っておくだけだったら、消費サービスに時間も興味も奪われてしまう。
それと、かつては親も、お金を払って子どもをあずけるんじゃなくて、いっしょにフリースクールをつくっていました。なので、スタッフも親たちとよく話し合っていました。でも、だんだんそれがいいサービスを求める感じになって、いっしょにつくっていく感じはなくなっていきました。なので、子どもが変化したという以前に、親や大人が変化したんだと思いますし、社会全体が市場化してしまったんだと思います。
金:韓国も、まったく同じですね。