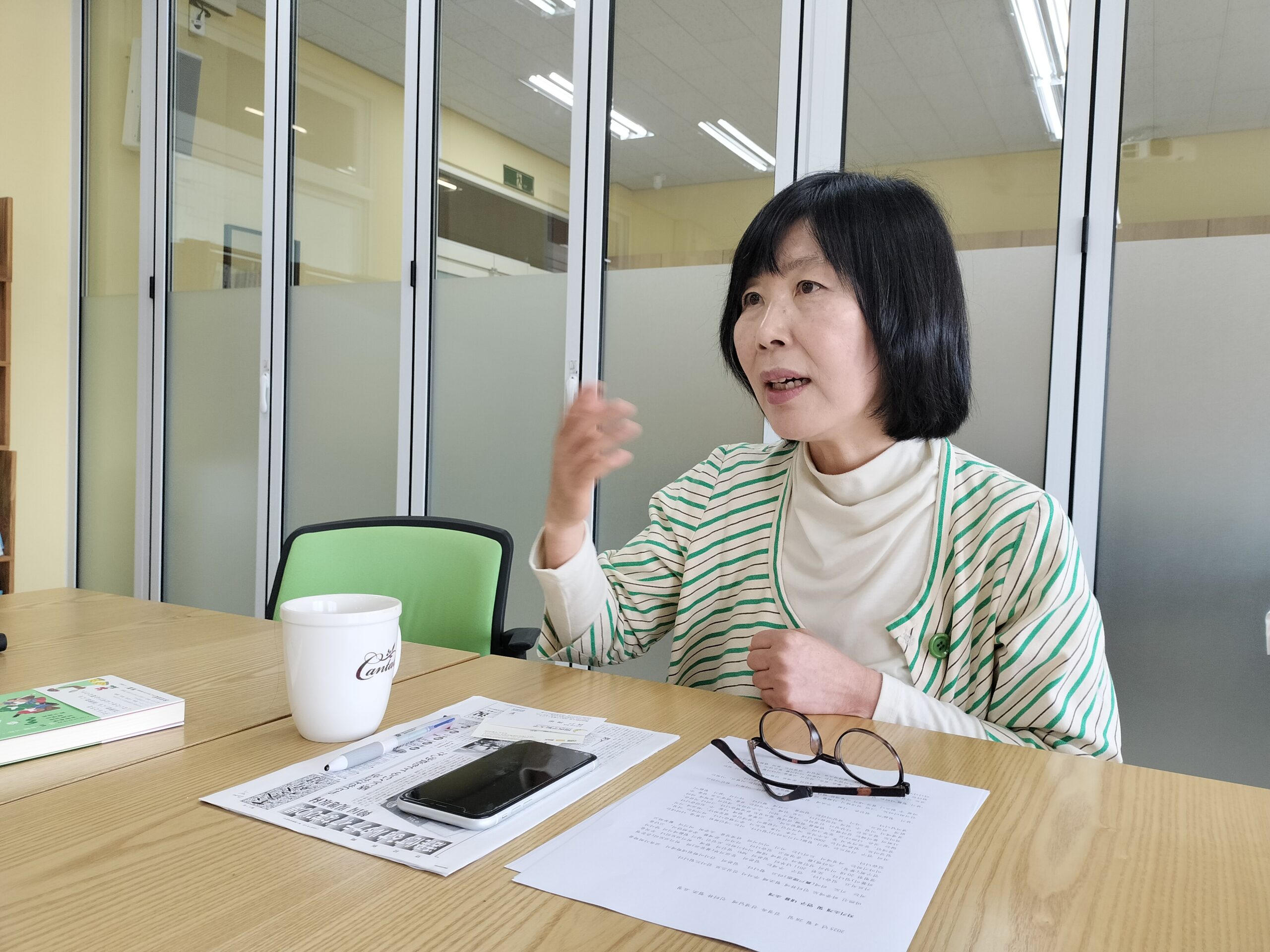1年制カリキュラムの導入
金:サランパンでは、集まる子どもたちがいて、いっしょに話し合ったり、映画を見たり、マンガを読んだり、ゲームをしたりしていました。先に企画があったわけではなくて、自然発生的にやっていたことですね。それも教育だと思いますが、子どもたちは、そこでいろんな活動をしていても、「自分たちは何もしてない」という感覚があると言っていました。何か積み上がっていくような感覚がない。それで、もっと積み上がっていくものがほしいというニーズがあって、カリキュラムが必要だということになったんです。もう一方では、もともと私自身が教育のあり方に関心があったということもありますね。そこで、自然発生的な教育じゃなくて、カリキュラムを設計して、それに沿って学ぶのも望ましいのではないかと思ったんです。それで、2006年に1年制の「空間ミンドゥルレ」を始めました。「空間」と名づけたのは、制度化された学校ではなく、子どもの自発性を大事にしながら、いろんな人が出入りする「空間」だという思いがありました。自分が行きたい進路を決める前に準備をする1年間ということで、いろんな授業やプロジェクト活動をする。この1年制のカリキュラムをつくるときは、それがほんとうに役に立つものなのか、確信はなかったんですね。でも、実際にやってみたら、けっこう役に立っていると思います。
貴戸:在籍者の年齢幅は13歳~18歳と幅広いですが、1年のカリキュラムをいっしょに学ぶということで難しさはありますでしょうか?
金:そのあたりはいろいろ議論して、1年で確実にできることを目標にしました。一般の学校でも代案学校でも、通常は3年とか6年の期間をかけて、いろんな目標を立てますね。でも1年となると、しぼらないといけない。そこで、ふたつを考えました。ひとつは、「学ぶことを学ぶ」です。人生でいろんな問題にぶつかっても、その問題をみずから解決しながら生きていくためには、「学ぶことを学ぶ」必要がある。もうひとつは、「ともに学ぶ」です。ひとりで孤独に学ぶのではなくて、いっしょに作業する。私たちはつながっているんだという感覚を持つ。
山下:「学ぶことを学ぶ」というのは?
金:何かを学ぼうと思っている人というのは、自分を尊重している人ですね。自分を愛している、自分が大事だから、学ぶ気持ちになれる。明日を楽しみにして、未来に期待できる。そんな感覚を持っていれば、何かを学び始める。だから、まずは自分を愛することができるように支えることが大事だと思っています。そのうえに、授業や活動がある。
未来に期待するというのは、未来にユートピアを期待するということではなくて、いろんなことを知ることで、そういう世界で自分は生きていくという期待を持つことができるということです。それと、自分のそばにいる人々のことを知ることが大事だと思っていて、それを授業や活動にしていて、いっしょに学ぶためのチームプロジェクト活動をしています。
「学ぶことを学ぶ」「ともに学ぶ」には、そのための力がいるんですね。そのとき、一番大事になるのは言葉だと私は思っています。ですから、ミンドゥルレでは言葉の学習に力を入れています。学校の教科書みたいなものは使っていないんですが、単語の正確な使い方とか理解力に関する勉強は、しっかりやっています。もうひとつには、自分の置かれている状況を理解できないと、いろいろ不安になったり、将来に希望を持つことができなかったりするので、そういう勉強は、しっかりやってます。子どもたちが、自分は何もできないという感覚にならないように努力しています。
ただ、いろんな年齢の子どもがいっしょに活動できるよさはあるものの、たとえば数学や科学は難しいので、そういう科目は、ミンドゥルレではやっていません。私たちはできないことはしません。でも、やっぱり数学や科学にも関心を持てたらいいなとは思いますね。
オデッセイスクール
貴戸:現在は、空間ミンドゥルレと並行して、「オデッセイスクール」をソウル教育庁から受託しているとのことですが、オデッセイスクールの概要と経緯を教えてください。
金:一般の公立高校の1年生が、1年間を代案学校で過ごし、出席扱いされる制度です。修学が遅れることなく、翌年度に2年次から復帰することが可能なんですね。2015年度から始まりました。学ぶ内容について行政からの干渉はありません。開始時は民間の3教室でしたが、現在は公立の2教室が加わって、5つあります。一つひとつの教室は独立していて、教育内容もそれぞれちがいます。
どの教室でも公立の教員が入っていて、1年間いっしょに教育をするんですね。そこで、子どもとの接し方や、子どもを見るまなざしを教員に学んでもらう。そして、その実践を経験した3人の教員たちが、2018年度と2020年度に公立の教室をつくったんです。

貴戸:オデッセイスクールは当時の教育監の肝いりで進められたそうですね。
金:そうです。ソウル市の場合、教育行政は独立しているので、教育監も選挙で選ばれるんです。2014年の選挙で、趙熙延氏が公約で「人文学系普通高校(=一般高校)の正常化」を掲げて当選し、その「人文学系普通高校の正常化」政策の一環としてオデッセイスクールが提案され、設計されました。趙氏は「30名のクラスで、5名は勉強するが、あとは寝ているだけになっている人が大半になっている。なぜ寝るのかといえば、それは子どもたちの問題ではなくて、学校の問題だ。この子たちが寝ないで、自分の人生を考えながら何かを学ぶ機会が必要だ」と言っていました。2014年に企画委員会が設置され、ソウル教育庁から3人、公教育の教員から1人、代案教育の側から2人の6名で討議して、2015年度に開始されました。かなり早くスタートできたのは、議論する人数も少なかったし、社会情勢と政治局面と民間の実践が一致したんだと思います。
制度の内と外で
貴戸:サランパンや空間ミンドゥルレは、制度の外に自発的に生み出された活動ですよね。一方で、オデッセイスクールは制度に位置づけられた活動だと思いますが、制度内でやっていくことに葛藤はありませんか?
金:すごく重要な質問ですね。ミンドゥルレを始めたころは、韓国で代案教育の実践をするにも、制度内では何もできなかったんですね。サランパンは、学校外の学び場として立ち上げたわけではなくて、息苦しさを感じて孤立している子どもたちが、自分を否定されずにいられる場があればいいという思いからできたものでした。
同じころ、韓国ではあちこちで代案学校がつくられ始めましたが、いずれも非認可の学校でした。でも、応援する人がたくさんいて、代案教育の考え方への社会的関心が高まっていって、学校制度内で教育にたずさわっている人たちも、この新しい教育運動に関心を持つようになっていきました。私たちが本や雑誌を出したり、研修や講演会を各地で開催したり、活発に運動をしたことも、社会的な影響があったと思います。
当時は、実情としては小さな存在でしたが、発信する言葉には力があって、いろんな反響がありました。教育の多様性の必要性が社会的に求められるなか、2006年、盧武鉉政権時代に、「学校設立に関する法律(学校設置法)」のうち「各種学校設立法」に〈代案学校設立に関する〉という下位条項が追加され、「設立に関するすべての基準は大統領令で定める」と制定されました。そして、その大統領令(施行令)によって具体的な条項が定められ、それにより10校ほどが認可されました。しかし、実効性が乏しく、その後はほとんど死文化した法律条項となっています。認可されるのは学校法人にかぎられていましたし、代案教育の内容や方法をちゃんと認めるものではありませんでした。
ですから、制度の中に入るのはよくないという意見も強くありました。制度の中に入ると、教員免許の資格が必要になったり、行政の監督下に入って、自由に活動できなくなってしまう。現在でも、教育行政は教員をすごく苦しめています。オデッセイスクールについても、そういう悩みがあります。たとえば旅行に行くには、1カ月前には計画書を出して、認可をもらわないといけない。宿泊場所についても規制がある。つまり、官僚的なんですね。それでは代案教育もダメになってしまう。それに、学校法人として認められるには土地も財産も必要で、それなりの規模が必要ですが、多くの代案学校は小規模で、そういう力がありませんでした。
一方で、制度外で一生懸命やっていても、子どもたちの息苦しさは変わらずあります。いろんな理由で学校に行かなくなる子がいるけれども、私たちのような場に来るにはお金もかかるし、まだまだ設備も不足しているし、悩みは尽きません。
ひとつ言えるのは、親たちが情報を知らないと、子どもには届かないということです。そういう意味でも、公教育の制度を変えていかないと、外で何をやっても、多くの子どもたちにとっては、力にならない。そこで、公教育の中にも多様性をつくり始めようということになっていったんですね。