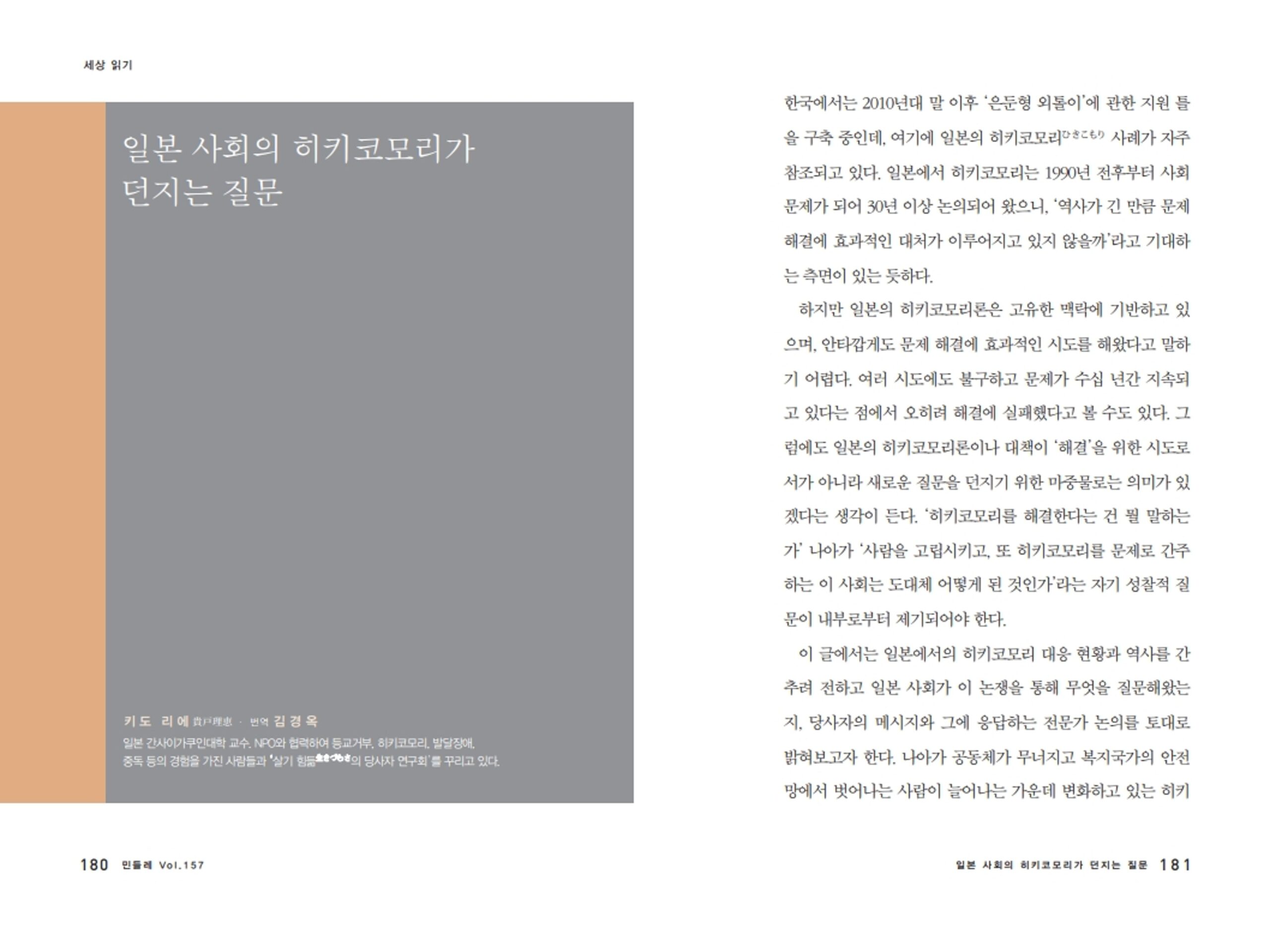3.当事者の主観的現実の重要性
以上で見てきたように、ひきこもりは日本では1990年代以降、専門家や支援者、親、行政によって社会問題として構築されてきた。ここにもうひとつ、重要なアクターを加えねばならない。ひきこもり経験を持つ「当事者」である。
当事者の主張が重要なのは、親とも支援者とも異なる立場から、ひきこもりをめぐる独自のニーズを表明しうるためだ。たとえば、ひきこもりの「解決」はしばしば「就労」や「人間関係の構築」だとされる。だがそれは、しばしば親・支援者にとっての見えやすい「解決」のかたちであり、当事者の立場からは異なる風景が見えてくる。
もっとも早い時期に当事者として発言した『「ひきこもり」だった僕から』の著者である上山和樹は、「ひきこもりとは<問い>である」(上山 2001:107)と書いた。会社員の父と専業主婦の母のもとに生まれた上山は、中学時代に不登校になり、その後ひきこもり、30歳を過ぎて「親の会」で自分の経験を語ったことをきっかけに支援やアルバイトといった活動に従事するようになった。上山の「問い」とは、突き詰めれば「自分であること」と「社会とつながること」を両立するにはどうすればよいか、というものだといえる。
「自分vs世界」。自分がいて、その自分が入っていけない「上手くいっている」世界がある。道ゆく人も、親も、昔の友人も、すべてが「世界」の住人。「世界」に仕込まれた諸々のルールが身に入っていて、うまくやっていける人々と、そういうルールの一つ一つに身がきしみ、なぜか「耐えられない」と感じてしまう自分のような人間と(上山 2001:84)。
それは大人になれば「自分の価値観と経済生活をどう両立させるか」という現実的な問いになって迫ってくる。この問いに周囲は「自分を変えて社会に適応せよ」と応じがちであり、その瞬間にコミュニケーションは途絶する。上山は、ひきこもり対応においてはまず本人の「問い」を共有し、親のものさしとは異なる本人なりの「自立」のあり方を受けとめることが重要だと示した(上山 2001:107-108)。
また、2014年に女性やセクシャルマイノリティのひきこもりに注目した当事者団体「ひきこもりUX会議」を立ち上げたひきこもり経験者の林恭子は、『ひきこもり・生きづらさについての実態調査』(ひきこもりUX会議 2019)のなかで、既存の支援では当事者が救われていない実態を明らかにしている。それによれば、約6割の人が行政による就労支援やその他の支援サービスを受けた経験があり、そのうち支援サービスに「課題を感じる」とした人は9割にのぼった。具体的には、就労経験のなさについて説教される、窓口をたらい回しにされ適切な支援にたどり着けない、外出はできるが就労は難しいという状態で利用できる支援がない、などの意見が表明された(林 2021:83-88)。そのうえで林は、「就労も大事だが当事者にとってまず必要なのは、居場所や安心できる人との出会いだ」(林 2021:88)とし、支援者向けの研修・講習には「当事者と支援者の温度差、支援イメージのちがいを埋めるためにも、必ず講師として当事者・経験者を入れてほしい」と語っている(林 2021:86-87)。
補足すれば、日本語の「当事者」という言葉には独自の文脈がある。フェミニストの上野千鶴子は、「当事者」を「(一次)ニーズの帰属主体」(上野 2008)と定義し、歴史的にパターナリズムのもとで専門家や親などによって自身のニーズを代弁されてきた障害者、女性、子ども、高齢者といった人びとが、主体性を取り戻し、「自分とは誰か、自分にとって何がよいか」をみずから定義していく自己解放の営みを「当事者主権」と名づけた(中西・上野 2003)。これに照らせば、ひきこもり問題の当事者とはひきこもっている本人であり、親や支援者は二次的な存在にすぎないのであって、問題解決のためには何よりもまず当事者ニーズの充足が重要だ、ということになる。
上山や林の主張に見られるように、「仕事をしているかどうか」は、しばしば親や支援者がもっとも大きな関心を寄せる点だが、当事者にとっては必ずしもゴールではない。「何のために働くか」という本人の内面的な納得が後回しにされた状態で、「世間に対して恥ずかしくないように」という他律的な動機から無理に就労したとしても、やがて息切れし、続けられなくなる場合も少なくない(貴戸 2022:217)。逆にいえば、就労しない状態が継続していても、本人が自己のニーズをつかみ、「何のために、何を、どのように」おこなうかについての納得できる答えを見出しつつあるならば、それはたしかに「回復」のプロセスにあるということもできる。
この点について社会学者の石川良子は、ライフストーリー研究の立場から、ひきこもりの困難は対人関係構築や就労といった行為の水準ではなく「いかに生きるか」という実存的な問いの水準にあるとし、当事者が「生きることへの覚悟、生きることや働くことの意味といったものを手にすること」(2007:229)がゴールになりうるとした。
近年では、ひきこもり当事者の主張は支援枠組のなかにも採り入れられるようになり、UX会議と政府のひきこもり施策が連携したり、厚生労働省が当事者の声を発信するといった取り組みが進められている。2023年には石川良子・林恭子・斎藤環が専門家/当事者の垣根を超えて対話し、当事者の立場からの問いを共有しながら「「ひきこもり」は「治療されるべき疾患」でも「解決されるべき問題」でもなく、目指すべきは「ひきこもることが問題視されない社会」である」という方向性を確認するに至っている(石川・林・斎藤 2023:88)。ここではひきこもりは、ひとつの生き方として脱問題化されるとともに、「ありのままを認めることが結果的に本人の内発的な変化を促す」という逆説の支援論が展開されていると考えることができる。
4.「階層的視点の欠如」批判をどう受け止めるか
他方で、当事者のアイデンティティを重視する実存主義的なひきこもり理解には、階層論的視点や社会政策的視点を後回しにしてしまうという課題が指摘されている。
たとえば教育学者の原未来(2022)は、「困り感がない」「葛藤がない」ように見える低階層出身孤立者の経験に注目し、不登校・ひきこもりを「就学・就労すべき」という規範意識を内面化しつつ「なぜかそれができない」という強い葛藤を抱える存在として描いてきたそれまでの中産階級中心の議論を批判している。
また、社会学者の川北稔は、現実には多様でありうる社会的孤立状態を「ひきこもり問題」と一括して把握する「ひきこもりの過剰拡張」(川北 2025:84)に警鐘を鳴らす。川北が危惧するのは、たとえば高齢の親と単身・無業の中年の子が同居し、さまざまな困難を抱える「8050問題」や、貧困や無業、病気などが複雑に結びついた孤立状態を「ひきこもり問題」とみなすことで、社会規範と自己の状況のあいだで葛藤を抱える「特定の心理状態」への共感的理解が優先され、個別具体的な支援が遠ざけられる可能性である。
現代社会では、伝統的な共同体の崩壊と階層的な分断が進むなか、多くの人が社会的孤立のリスクに晒されており、孤立者を経済的・関係的に包摂する社会的枠組みが求められている。ひきこもりはそうした孤立のひとつの形態にすぎず、本人や親の高齢化に伴って、貧困、病気、ケアの不足といった一般的な生活困窮の問題にスライドしていく現実がある。その意味で、制度・政策的に考えれば、今後のひきこもりへのアプローチは、多様な価値や関係性構築を追求する当事者活動や一部の支援活動を含みつつも、その大半が生活上の諸問題に複合的に取り組む孤立支援に回収されていくのかもしれない。実際に川北は、ひきこもりという用語を心理的状況からくる対人交流の欠如に限定し、包括的な問題記述の概念としては社会的孤立を用いることを提案している(川北 2025)。
しかし、社会的孤立が、日本社会において他ならぬひきこもりというかたちで現れたことの意味を考えるならば、この概念を切り詰めることには慎重でなければならないと私は思う。ひきこもりをめぐって積み上げられてきた議論は、第二次世界大戦後の日本において、社会なるものがいったいどのようにつくられてきたのか、さらには「社会的存在であること」を脅かされた人間がいかにそれを取り戻しうるか、と問いうる射程を持っている。最後にこの点について考えてみよう。