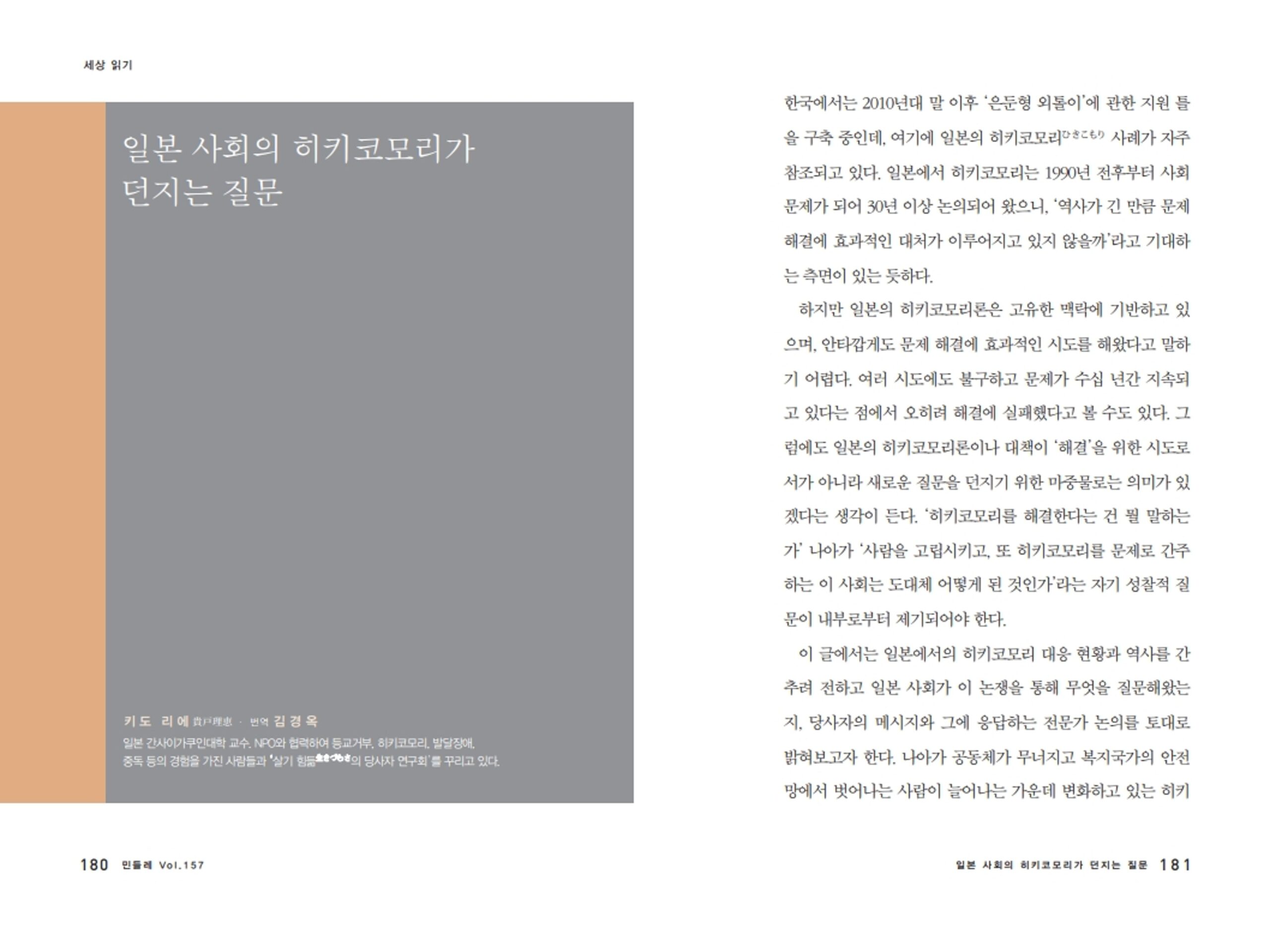2-2.統計
2023年発表の内閣府による『こども・若者の意識と生活に関する調査』では、ひきこもり状態とカウントされた人は15-34歳の2.05%、40-64歳では2.02%であり、併せると全国で46万人にのぼると推計された。この数字は多いが、本調査では「ふだんは家にいるが、自分の趣味に関する用事の時だけ外出する」「ふだんは家にいるが、近所のコンビニなどには出かける」などの人も「ひきこもり状態」に含まれており、これを除いて「自室からは出るが、家からは出ない」「自室からほとんど出ない」のみにかぎれば、15-39歳で0.36%、40-64歳では0.14%となる。「ひきこもり状態」とされた人の8~9割は趣味の用事やコンビニなどに出かけていることになる(川北 2025:179)。
40~64歳の「中高年のひきこもり」については、かねてより家族会を中心にその存在が指摘されていた。2019年発表の調査で初めて統計が取られ、その年齢の1.45%にあたる61.3万人がひきこもり状態にあると推計された。2010年代後半ごろから80代の親と50代の無業の子どもが同居し様々な問題を抱える「8050問題」が社会問題化していた。
ジェンダーについては、斎藤環が1998年の時点で、第一子の男性に多く、女性の事例はあるが長期化しないと書いていた(斎藤 2020:36)。その後の調査も、おおむね7~8割が男性という結果が多くなっている。だが内閣府調査(2023)では、15~39歳では女性が45.1%、40~64歳では52.3%とほぼ半数が女性であることが明らかになった。これには、「女性のひきこもり」に対する関心が高まったことや、それにともない妊娠・育児・家事を担う人もひきこもり状態に含めるとされたことが影響している。ジェンダー視点への注目のきっかけとなったのは、2016年から「女子会」を開催する当事者団体「ひきこもりUX会議」などの活動により、ひきこもる人のなかで女性や性的マイノリティの存在が可視化されたことだった。
ひきこもりはきわめて社会的で可変的なカテゴリーであり、実態がどのように変遷しているのかはこれらの統計からは分かりにくい。ともあれ過去15年の変化をみれば、「10~30代の男性」を中心とするイメージでとらえられていたひきこもりが、中高年や女性、性的マイノリティにおいても発見され、統計上の数字を膨らませながら社会的関心を喚起し続けてきたことが分かる。
2-3.制度・政策的取り組み
1990年にひきこもりは『青少年白書』(総務省青少年対策本部 1990)で取り上げられ、「若者の非社会的行動」とされた。1991年に「ひきこもり・不登校児童福祉対策モデル事業」が開始されたものの、支援は限定的だった。ひきこもりは一部の支援者や新聞記者、精神科医によって注目され始めたが、1990年代にはこれ以外の制度的な取り組みは存在しなかった。
2000年代以降、厚生労働省が中心となり支援の整備が進められていく。2003年、同省は「10代・20代を中心とした「ひきこもり」をめぐる地域精神保健活動のガイドライン」を発表し、援助の技法や支援プログラムの可能性などを示した。同年、一般的な若者への自治体をベースとした就労支援として、ヤングジョブスポット(のちの地域若者サポートステーション)が開始される。
2005年には「若者自立塾」という集団生活のなかで生活訓練や職業訓練をおこなう宿泊型支援事業が始まるが、2010年に廃止されている。
2009年、「ひきこもり対策推進事業」がスタートし、行政が運営するひきこもりに特化した相談窓口である「ひきこもり地域支援センター」が各都道府県と政令指定都市に設置された。これにより当事者や親が最初に相談する窓口が整備され、社会福祉士や精神保健福祉士などの資格を持つ専門相談員による面談や情報提供、居場所づくり、就労支援などがおこなわれるようになった。
翌2010年、「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」が発表され、医療的対応の必要性を強調するとともに、「ひきこもり支援の多次元モデル」に基づいて具体的な対応が示された。
さらに2018年には「ひきこもりサポート事業」、2024年には「ひきこもり支援ステーション事業」が開始され、市町村レベルでの地域に根ざした支援をおこなう枠組が整備された。2024年、「ひきこもりVOICE STATION」というポータルサイトが開設され、ひきこもりに関する情報に加えて、当事者や家族、支援者の声が発信されるようになった。2025年には「ひきこもり支援ハンドブック 寄り添うための羅針盤」が出され、ひきこもり支援の対象を広げるとともに、「自立」ではなく「自律」を目指すとして本人の意志の尊重が確認された。
社会学者の石川良子は、日本社会におけるひきこもりの問題化の歴史を、①1980年代までの不登校(登校拒否)と重ねられていた時期、②1990年代の不登校から分離した時期、③2000年代前半の独自の問題領域を形成した時期、④2000年代後半の若者無業者問題と重ねられた時期、⑤2010年代前半の発達障害やライフスタイルなど多様な問題と接合した時期、⑥2010年代後半以降の失業や生活困窮が加わった時期、に分けて捉えている(石川・林・斎藤 2023:24-27)。行政の支援は、ひきこもりが独自の問題系を確立した後の2000年代にスタートし、若者の自立支援や生活困窮者支援などその時々に提起された近接の社会問題と接続しながら展開していったと言える。
2-4.民間支援の展開と課題
他方で、民間によるひきこもり支援は、不登校問題との関連で1980~90年代にスタートしたものもあり、より歴史が古く、支援の在り方も宿泊型や訪問型(アウトリーチ)などを含め多様である。厚生労働省の調査によると、2018年の時点でひきこもり地域支援センターによって把握されているNPO等をはじめ社会福祉法人や社会福祉協議会といった民間支援団体の数は、全国で1089にのぼった(厚生労働省 2018)。
著名な民間支援団体としては、訪問活動や寮での共同生活を通じた自立を目指す「NPO法人ニュースタート事務局」、共同生活寮や海外とのつながりを重視する「K2インターナショナルグループ」、無業の若者の就労支援に軸足を置く「NPO法人 育て上げネット」などがある。また、秋田県藤里町の社会福祉協議会による、地元名産のまいたけを使ったキッシュ販売などを通じてひきこもり支援と地域活性化を両立させた「藤里方式」も知られている。
民間支援は、上述したような団体では国や自治体の支援事業を受託するなど官民連携で進められる場合もあるが、小規模で独自の取り組みではそうでないものも多い。たとえば、専門的なノウハウが介在する就労支援や心理支援とは異なる、当事者による居場所活動やひきこもりに関するイベント開催、雑誌やHPでの情報発信などは制度的枠組みから漏れ落ちる傾向にあり、資金難のなか従事者のボランティア精神で運営されている場が少なくない(山下 2009; 伊藤 2022)。
民間団体は、ひきこもりの理解を促進するうえで重要な役割を担ってきた一方で、なかには「引き出し屋」と呼ばれる本人の意志に反して暴力的に自宅から引き離す問題の多い支援が存在してきた歴史も、忘れてはならない。古くは不登校や「問題児」を体罰により矯正するとして複数の死者・行方不明者を出した1979~1982年の「戸塚ヨットスクール事件」があるが、類似の介入形態はけっして過去のものにはなっていない。2006年には名古屋の「アイ・メンタルスクール事件」が起き、26歳の「ひきこもり」とされる男性が無理やり自宅から連れ出され、暴行や手錠・足かせによる拘禁を受けたのちに外傷性ショックで死亡した。2017年には東京の「あけぼのばし自立研修センター」で、やはり26歳の「ひきこもり」状態にあった男性が暴力的に自宅から連れ出され施設に監禁されたのち「研修先」で死亡している。2020年には類似の暴力的な運営施設に対して元入所者が集団訴訟を起こし、その後賠償命令が出されている。2021年には、当事者や専門家、親が関わる「暴力的「ひきこもり支援」施設問題を考える会」により、「ひきこもり人権宣言」が発表された(暴力的「ひきこもり支援」施設問題を考える会 2021)。
死亡事件や訴訟に至るのは「一部の悪質なケース」だとの見方もありうるが、同時にそうしたケースと一般的な「支援」は、連続的である面もある。Miller&Toivonen(2010)は、「戸塚ヨットスクール」と「K2インターナショナル(旧コロンブスアカデミー)」について、ヨットの訓練から始まり死亡事件を起こした点で共通性を持つとし、更生理念を比較分析して、前者を「規律型」、後者を「受容型」と対照的に位置づけた。そのうえで、受容型アプローチが国家的な支持を得つつある一方、規律型アプローチも一部で支持される日本の「更生」をめぐる論争的状況を指摘した。だが同時にこれは、より一般的な「受容型」施設においても、ときに暴力被害は生じうる、という現実を示しているようにも見える。
一般的な話として、訪問支援や宿泊型支援では、しばしば支援の依頼者は親であり、「当事者の意志」が二次的に位置づけられるという構造的な問題を抱えている(HIKIPOS 2024)。「嫌がる本人を無理やり連れだす」のが暴力であるのはわかりやすい。だが、「将来どうするのか」といった「正論」に基づく「説得」や、ひきこもっていることにどうしようもない罪悪感を抱える本人の意識に働きかける「話し合い」の結果として「本人の同意」が調達されるような場合はどうだろうか? 親や支援者にとっては「対話」であっても、当事者から見れば「強引な説得=暴力」である、ということはありうる。あらゆる支援現場が「自分の場は無関係」と考えることなく、当事者の意志の尊重や個人の抱える特性への理解、緻密な関係調整などを丁寧に継続する必要があると、自戒を込めて思う。
さらに、こうした暴力的な介入が繰り返される背景のひとつに、ひきこもり対応を家族に丸投げする根深い家族ケア規範があることも忘れてはならない。長期化する深刻な「ひきこもり」を抱え込んだ末、孤立し追い詰められた親が、高ければ数百万円から1千万円以上にもなる費用と引き換えに、子どもを暴力的な業者に託すケースがある(高橋 2025)。支援の質保証や支援者の倫理に加えて、根本的には家族の抱え込みを減じるような実効性ある共助の仕組みが求められている。